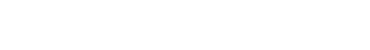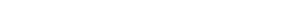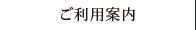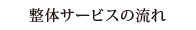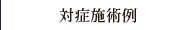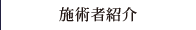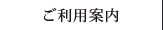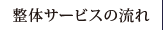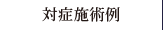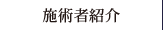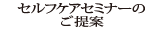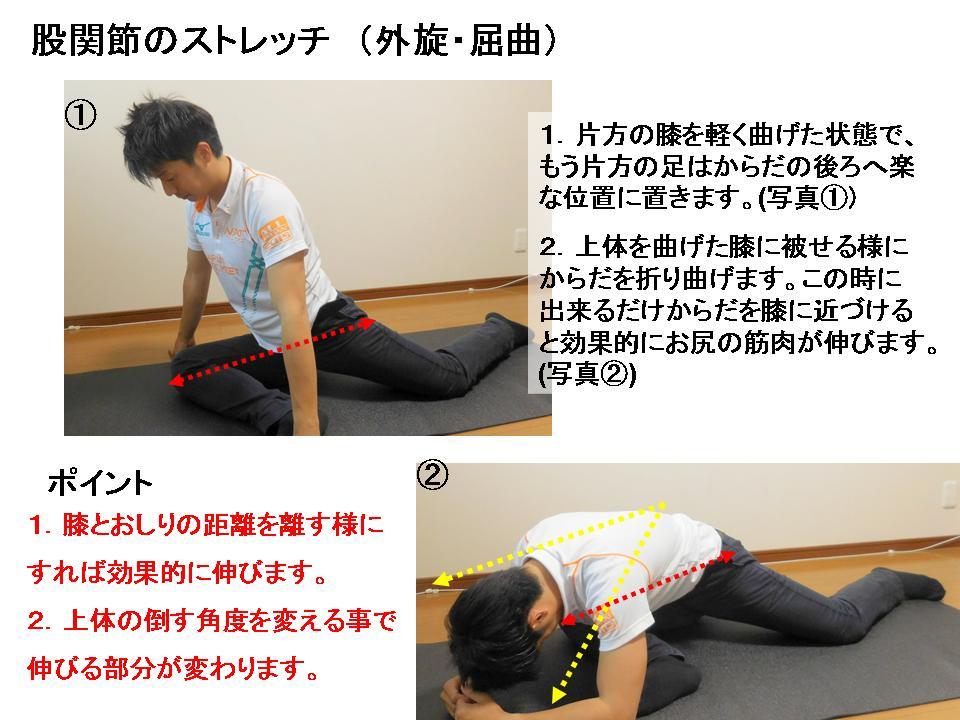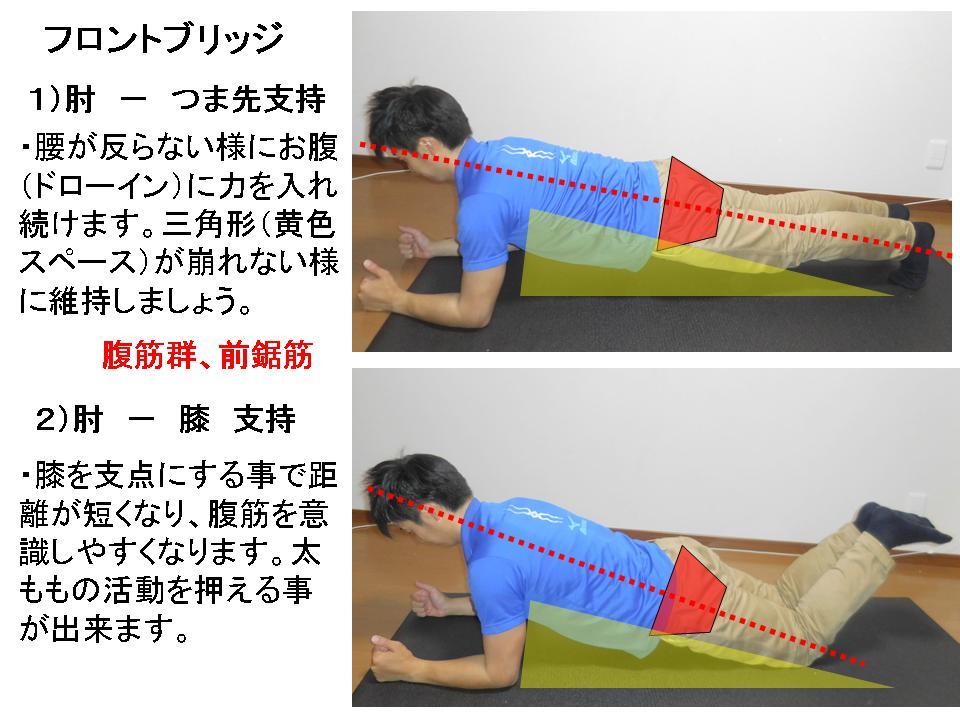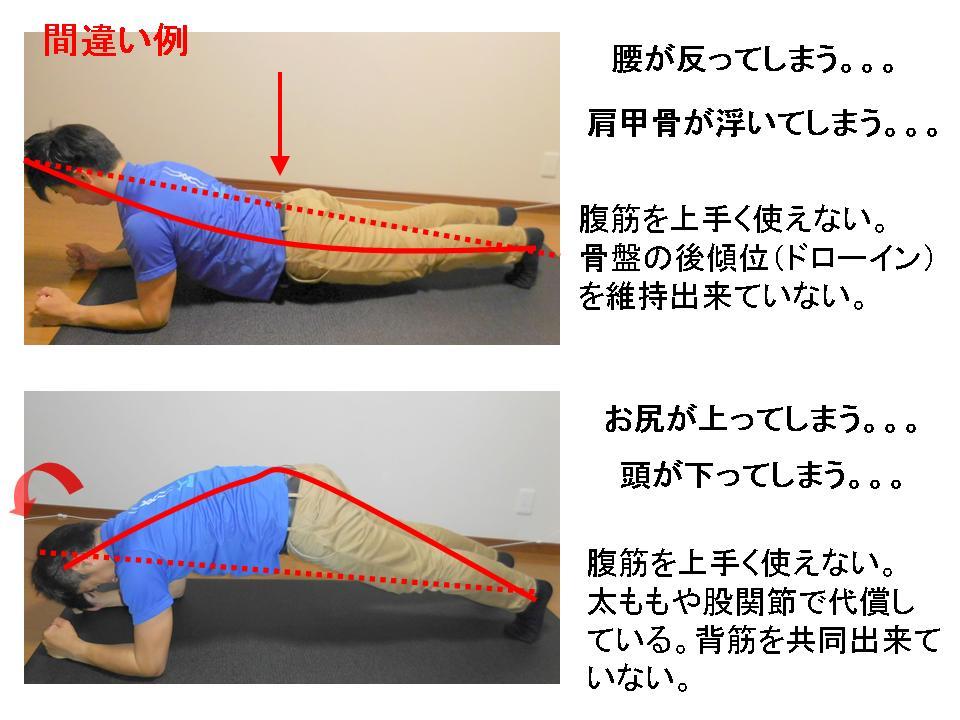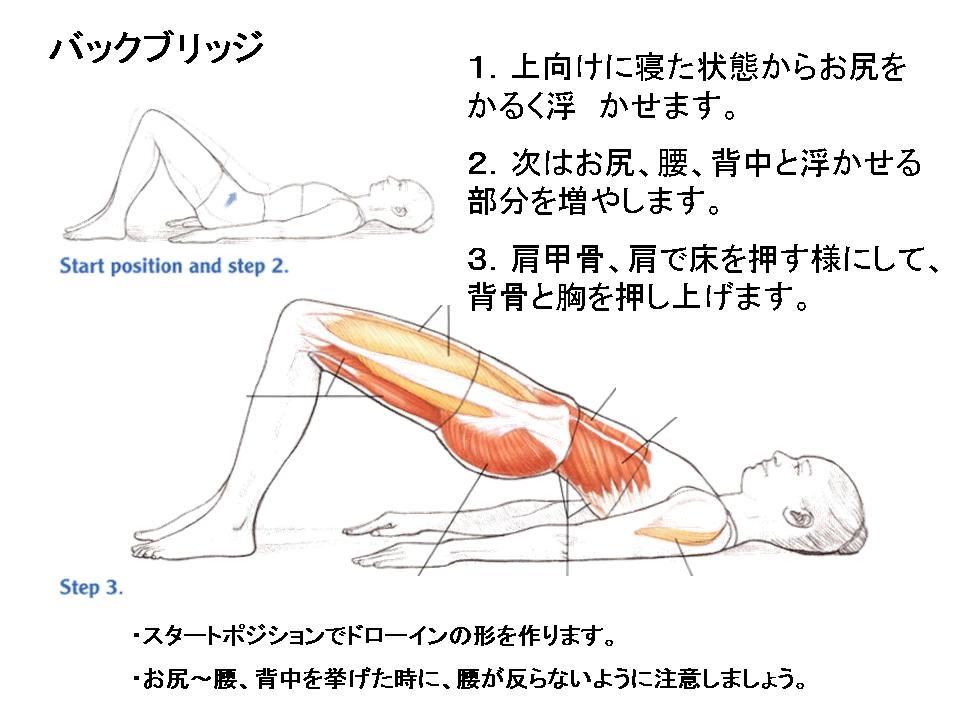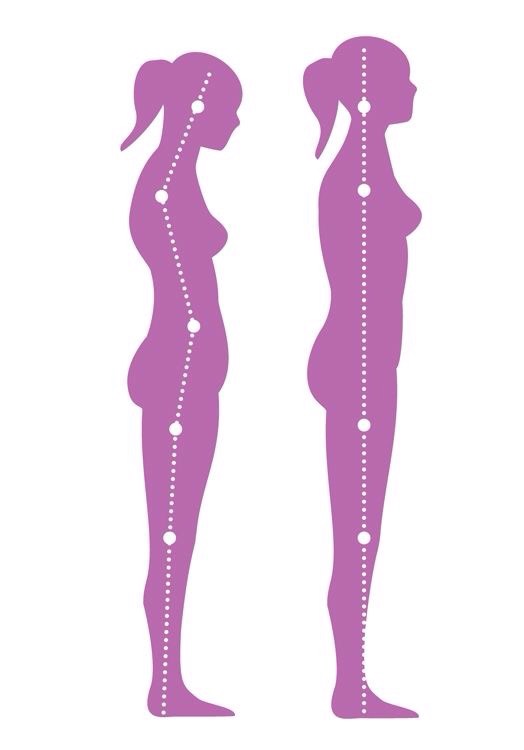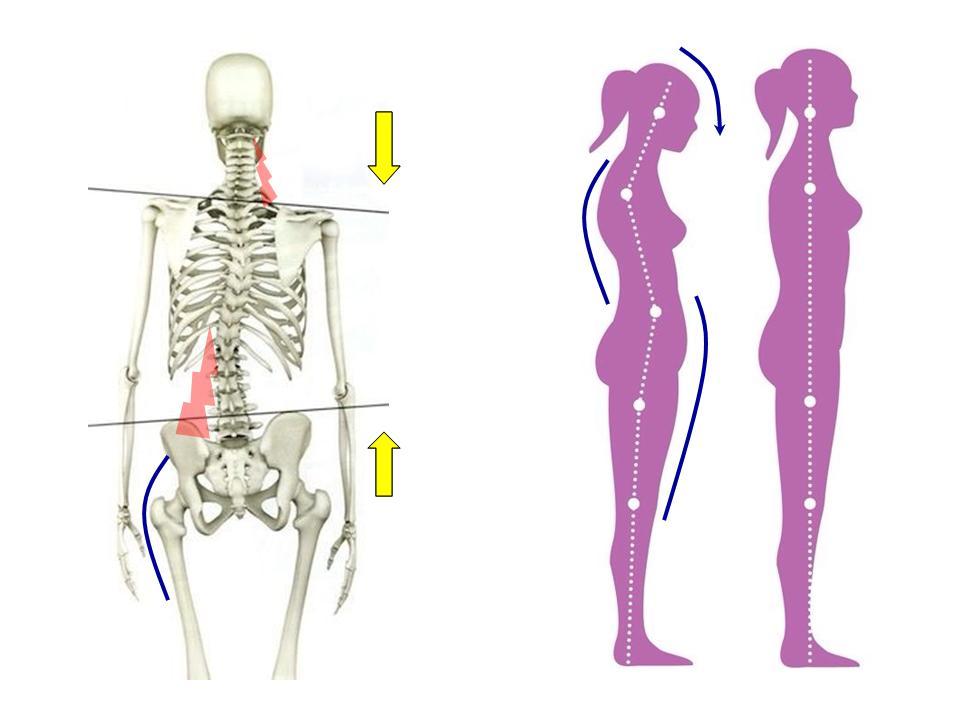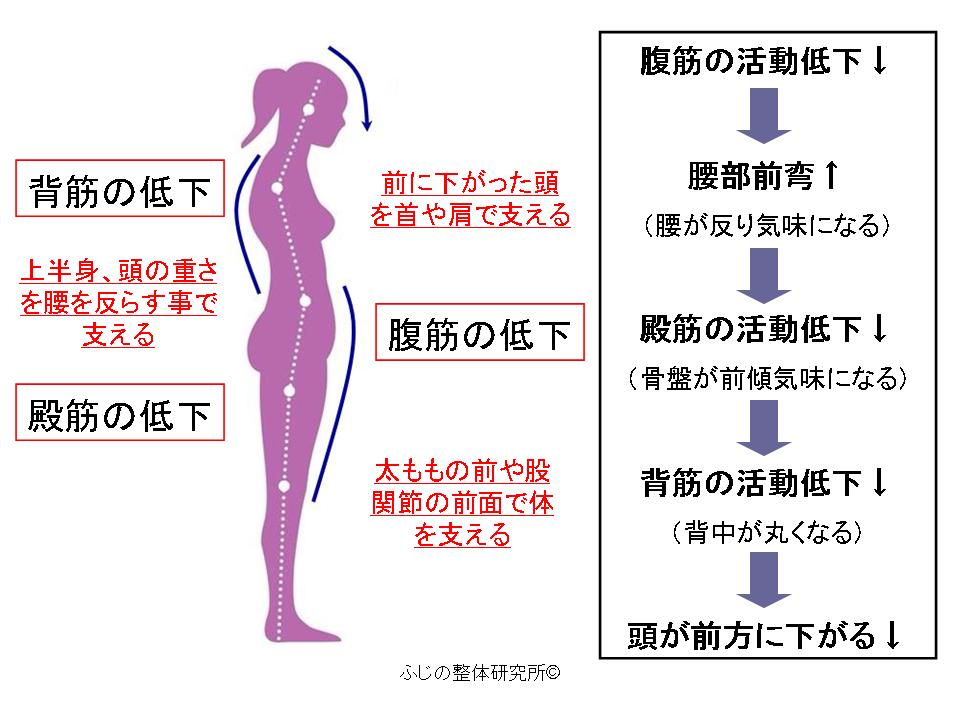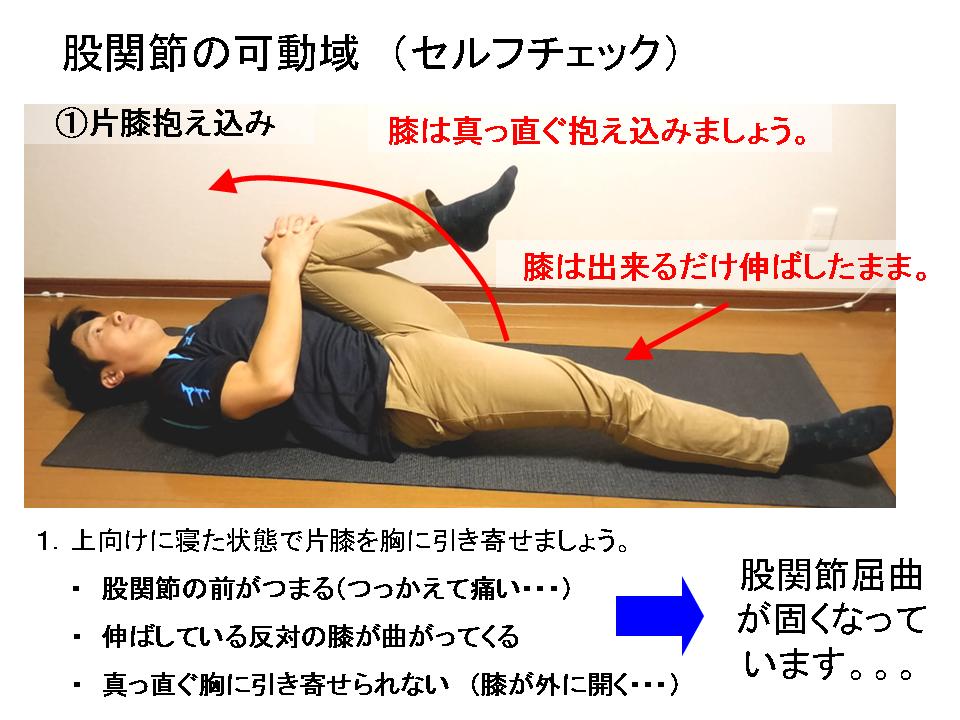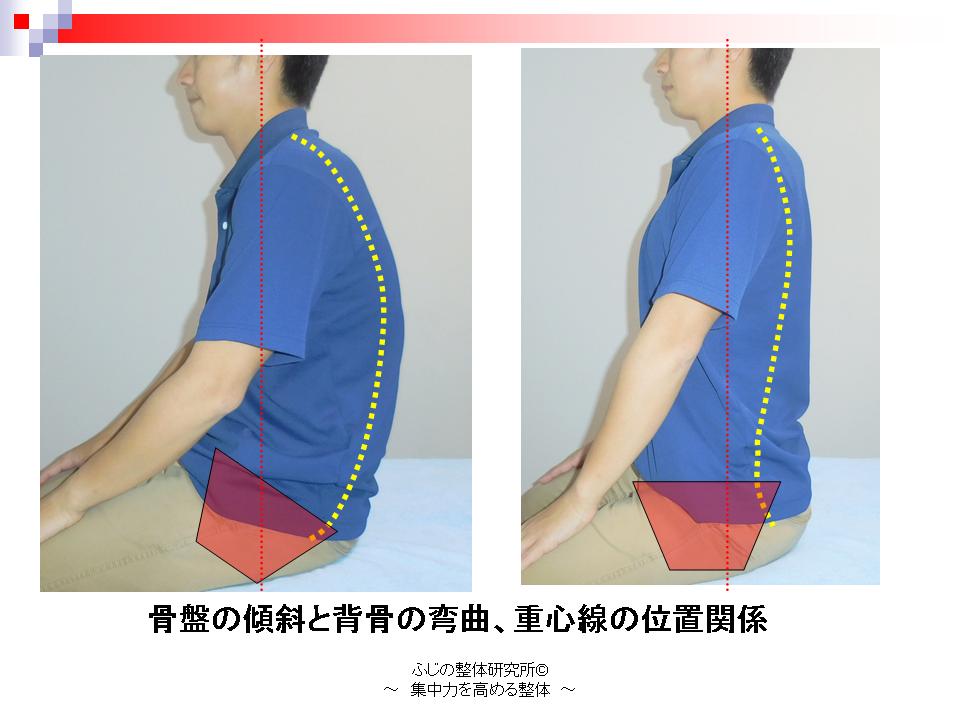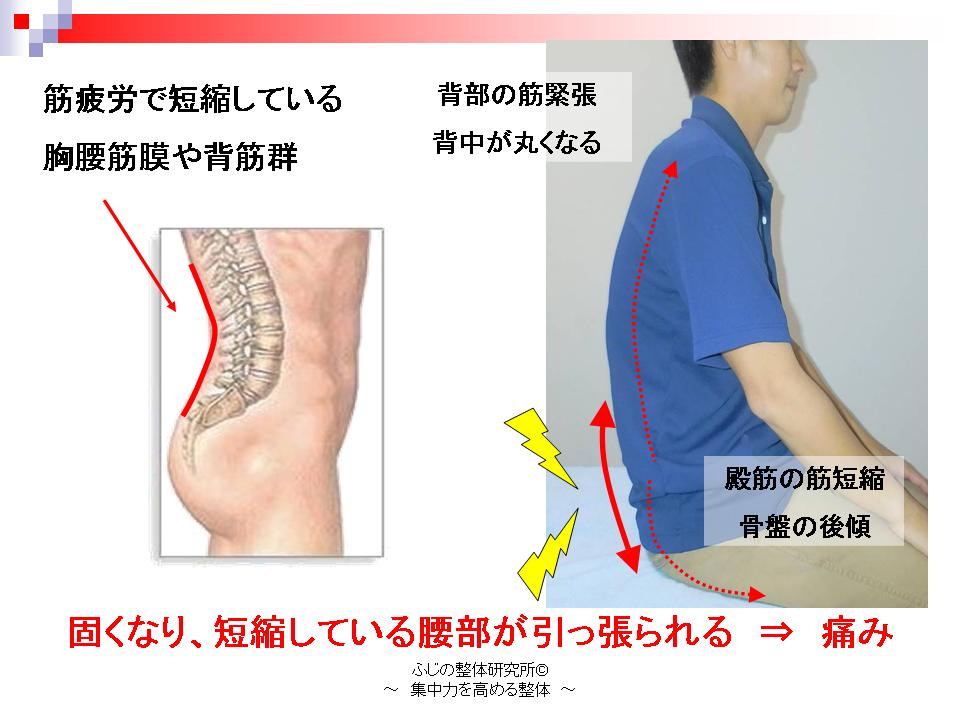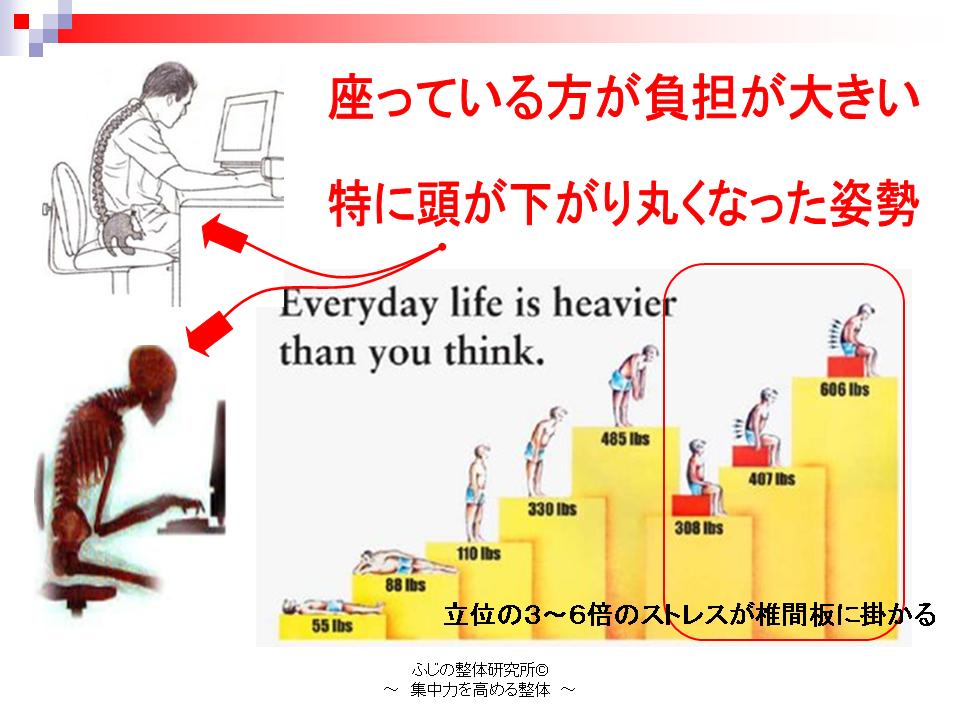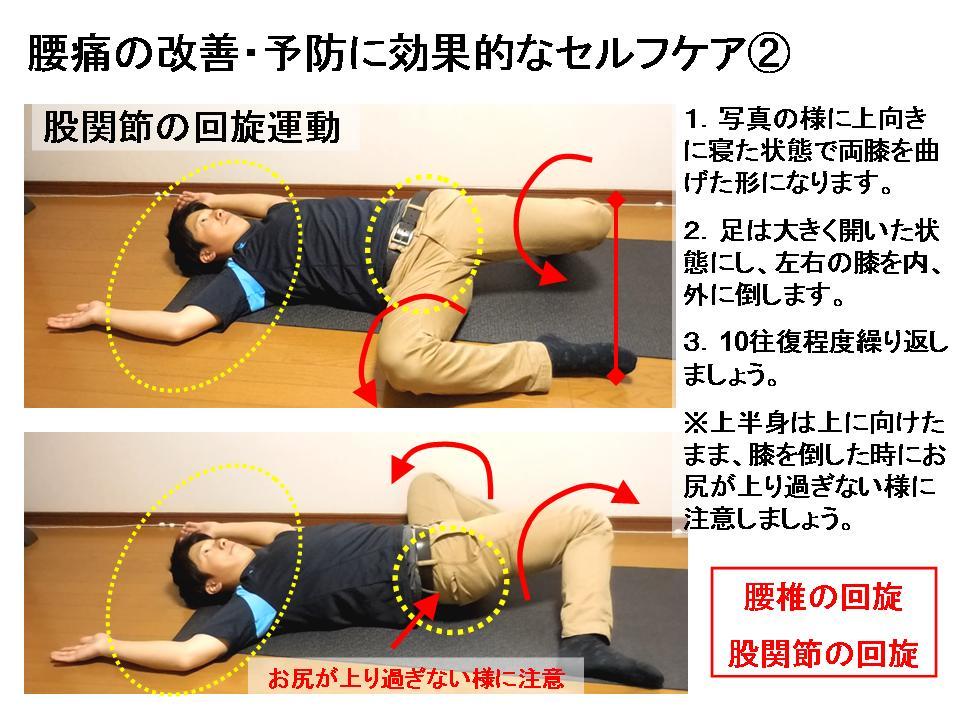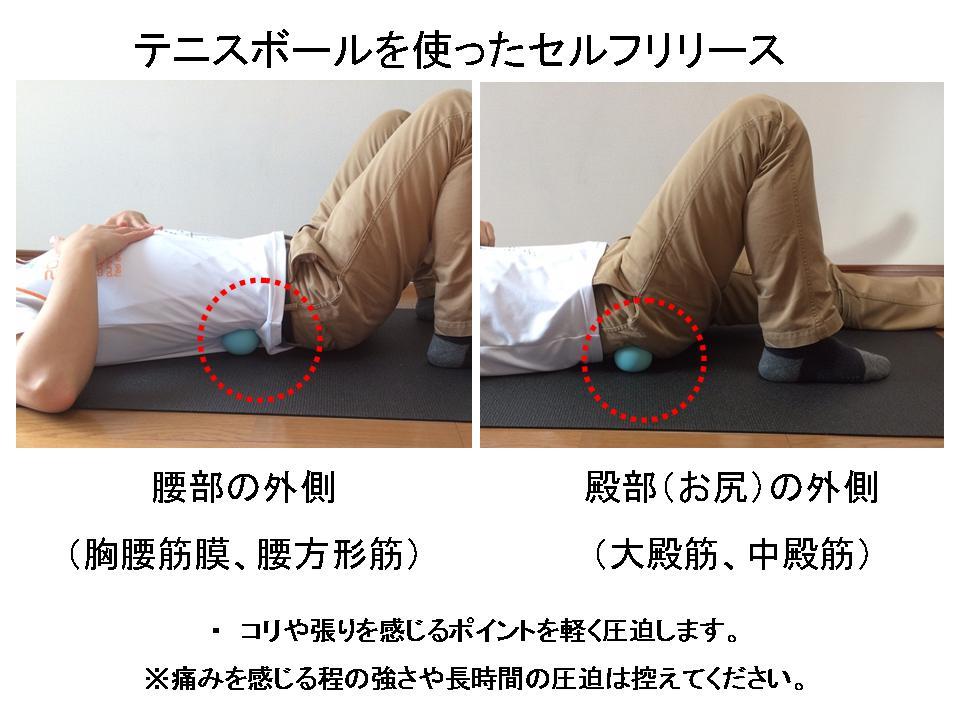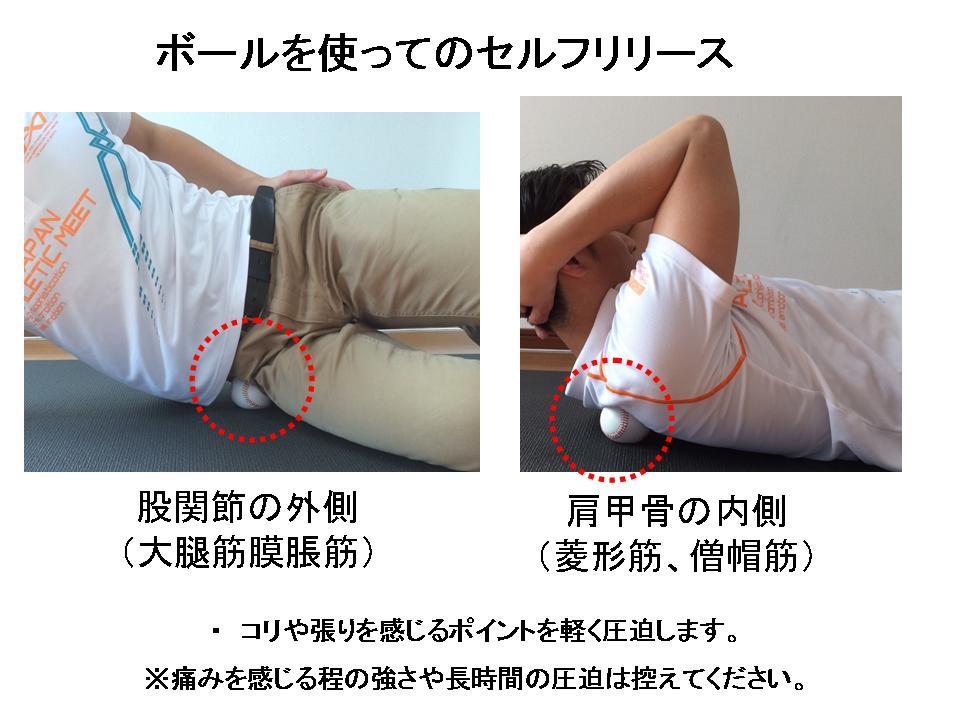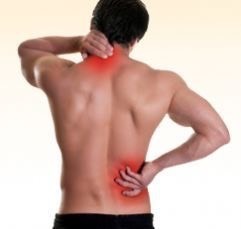腰痛に悩む方へ・・・ 改善・予防の運動プログラム②
今回は体幹トレーニングのフロントブリッジについて解説します。
・スポーツや運動時に腰が痛い、又は 運動後や翌日の腰痛・・・
・年に数回はぎっくり腰の様な突発的な腰痛がある・・・
・慢性的な腰痛にいつも悩まされている・・・
・下っ腹が出て太ってきた・・・
これら1つでも該当する方は基本的に体幹部の筋機能が低下
しているか、骨盤~腰椎の姿勢が悪化しているか。。。
腰痛のリスクファクターが存在するでしょう。
前回のバックブリッジとは対照的に、このエクササイズでは
体幹部の前面を主に働かせる事が出来ます。
※前回の続きとして合わせてご覧ください。
特に前面では腹筋群が内臓を支える役目を担います。
この腹筋群が低下してたり、姿勢的に腹筋群が働きにくい状態に
あると、腰椎、骨盤の安定性が低下し、内臓が下方に下がって
しまう事になりかねません。
腹筋群の機能低下は結果として腰痛になりやすい状態になります。
⇒ からだの前面で壁を作り、腰椎、骨盤を支える機能が低下していまい
腰椎の前弯の増強や骨盤の前傾が過度に起こり、腰部へのストレスを
増悪させてしまいます。。。
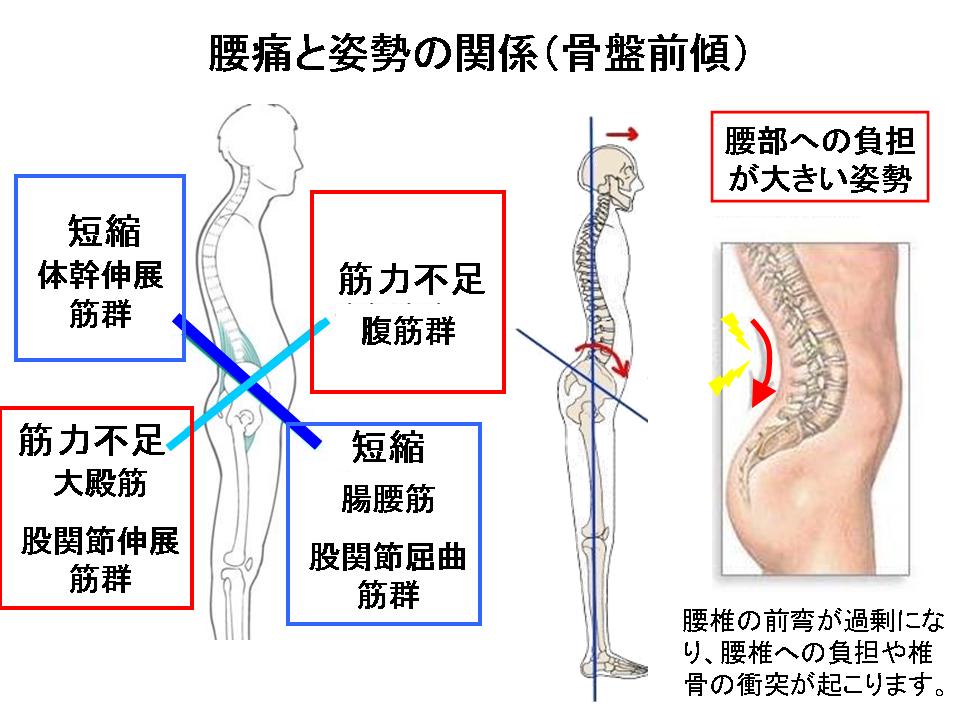 背筋と腹筋の両方で、骨盤~脊柱を挟みこむ様に働く事で
骨盤~脊柱が安定し、動作時の痛みやスポーツ動作などでの
腰痛を予防していく事で出来ます。
背筋と腹筋の両方で、骨盤~脊柱を挟みこむ様に働く事で
骨盤~脊柱が安定し、動作時の痛みやスポーツ動作などでの
腰痛を予防していく事で出来ます。
フロントブリッジ
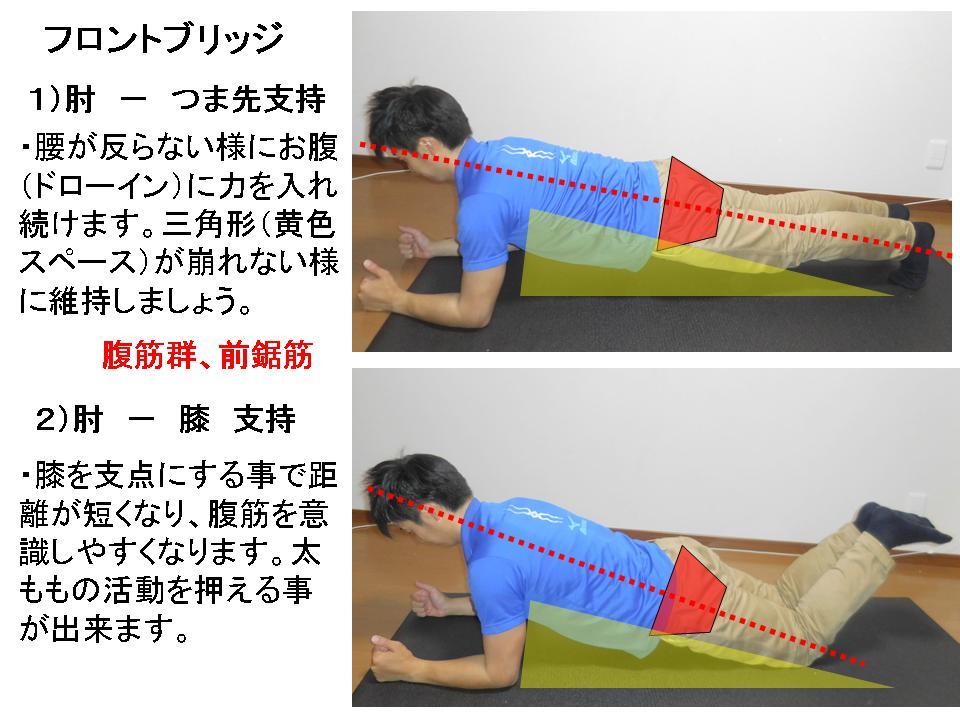
まずは 下の写真から取り組んでみましょう。
肘 - 膝 で支える事により、体幹を支える長さが短いので
その分負荷が軽く、正確に体幹部に効かせる事が出来ます。
体幹トレーニングに慣れていたり、体力のある方は
上の写真の方法で取り組みましょう。
☆60秒間キープ を 3Set 繰り返しましょう。
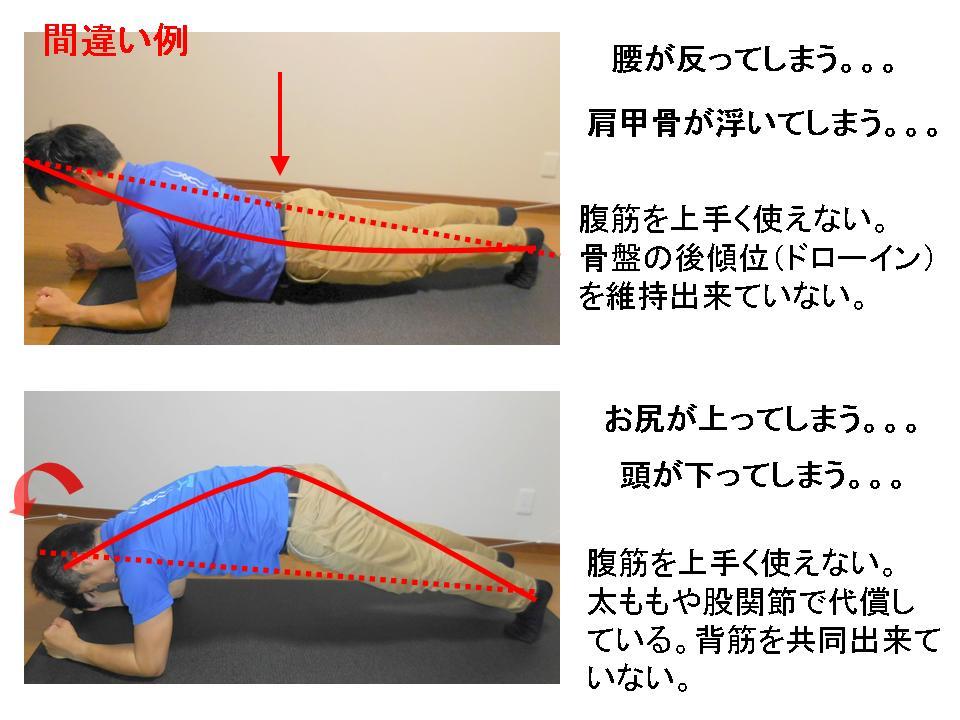 上の写真は間違ったフォームの例です。
特に女性は上の写真の様に、腰が反ってしまいがちです。
体を一直線で保てるようにフォームに注意しましょう。
上の写真は間違ったフォームの例です。
特に女性は上の写真の様に、腰が反ってしまいがちです。
体を一直線で保てるようにフォームに注意しましょう。
ポイントになるのは、やはりからだの中心部から順番に力と形を作る
事にあるようです。決めてはドローインが重要。
よく見られる間違いのフォーム
1.腰が反っている
2.肩甲骨と胸郭が分離している
3.背中が丸くなっている
4.頭が下がり肩に力が入る
それぞれに重なる点もありますが、これらの間違いは多く遭遇します。
体幹トレーニングは、からだの中心部を鍛えるので軸が安定する
感覚と、姿勢を安定する事が得られます。
スポーツだけに限らず、健康管理や仕事でのパフォーマンスや
姿勢やスタイルを維持、向上させるセルフプロデュースにも効果的です。
どんなトレーニングやストレッチでも共通して言える事ですが
重要な事は、体のどの部分を使い、どの部分が伸びているのか?
をより意識する事です。
感覚を巡らせる事で脳~筋肉の神経伝達が促され効果が生まれます。
トレーニングが見た目で同じフォームや形が出来ていても
体の感覚とずれていたり、使ってほしい筋肉が間違っている事もあります。
これでは効果が生まれませんので、注意しましょう。
フロントブリッジのポイント
効果的な方法(ポイントとなるフォーム)
・あごを引いて頭からつま先を一直線にする
・骨盤を後傾気味にする(ドローイン)
ポイント
・つま先を曲げたまま、足先方向に軽く押す事で
お尻やハムストリング、に力が適度に入ります。
・両肘を外に押し広げる様に力を入れる事で
肩甲骨を支える筋肉が活動します。
⇒ 肩甲骨を上手く固定できていない例も多いです。
2つのポイントは普段指導している際に効果的ですので
是非意識してみてください。
***************************************
「 ~ 集中力を高める整体 ~ 」
ふじの整体研究所
FaceBook :https://www.facebook.com/fujino.seitai
Twitter:@fujino_seitai
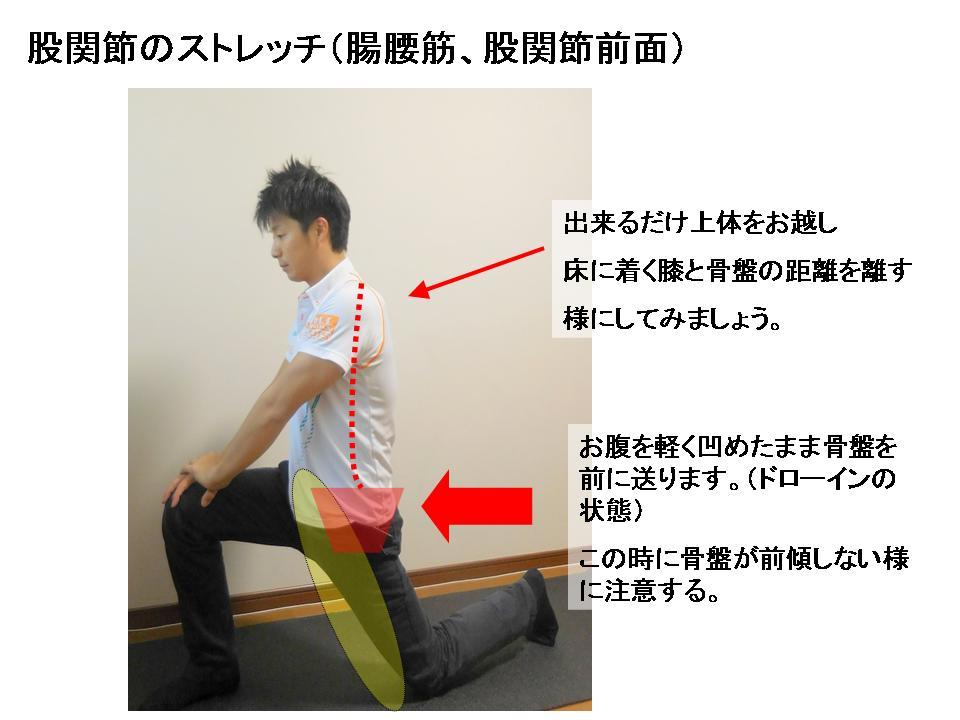
伸展型での腰痛を抱える方には 特に効果的な方法ですが 前屈、後屈関わらずに 腰部の痛みの改善や予防 姿勢の改善などには効果的ですので 是非紹介した内容を取り組んでみてください。