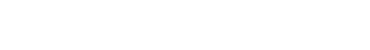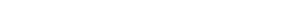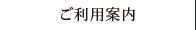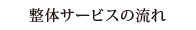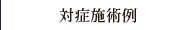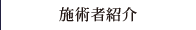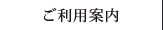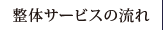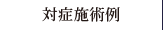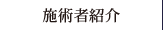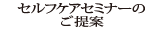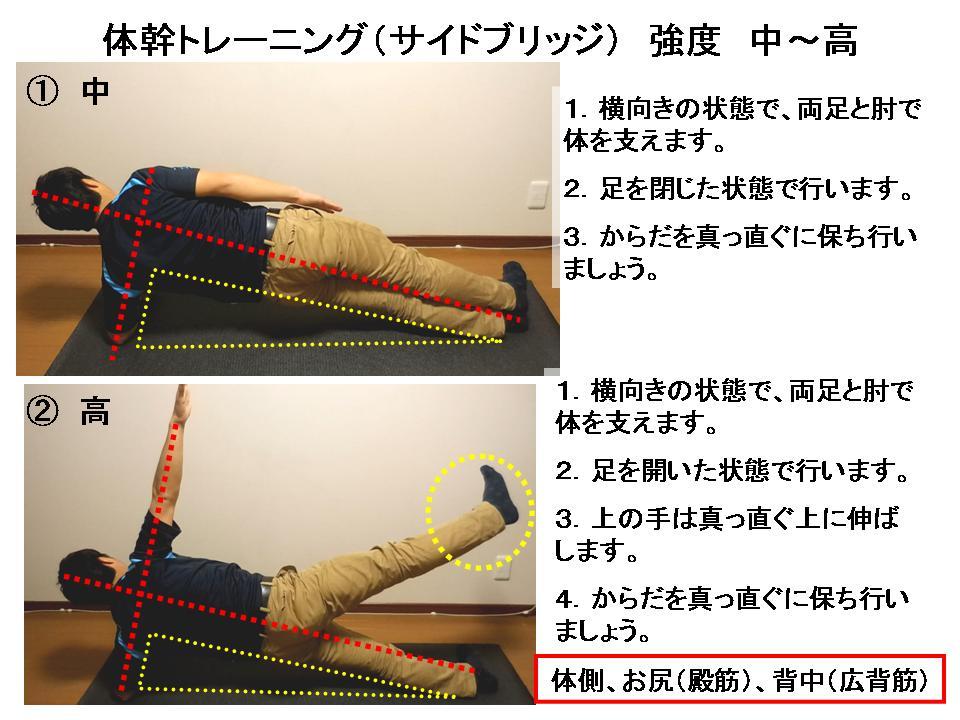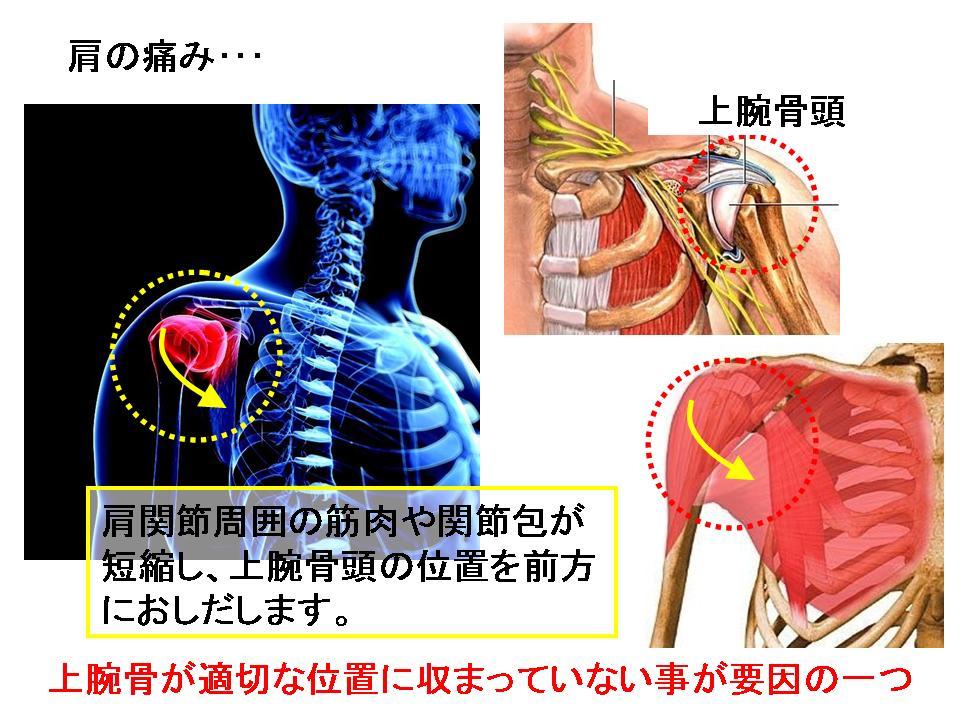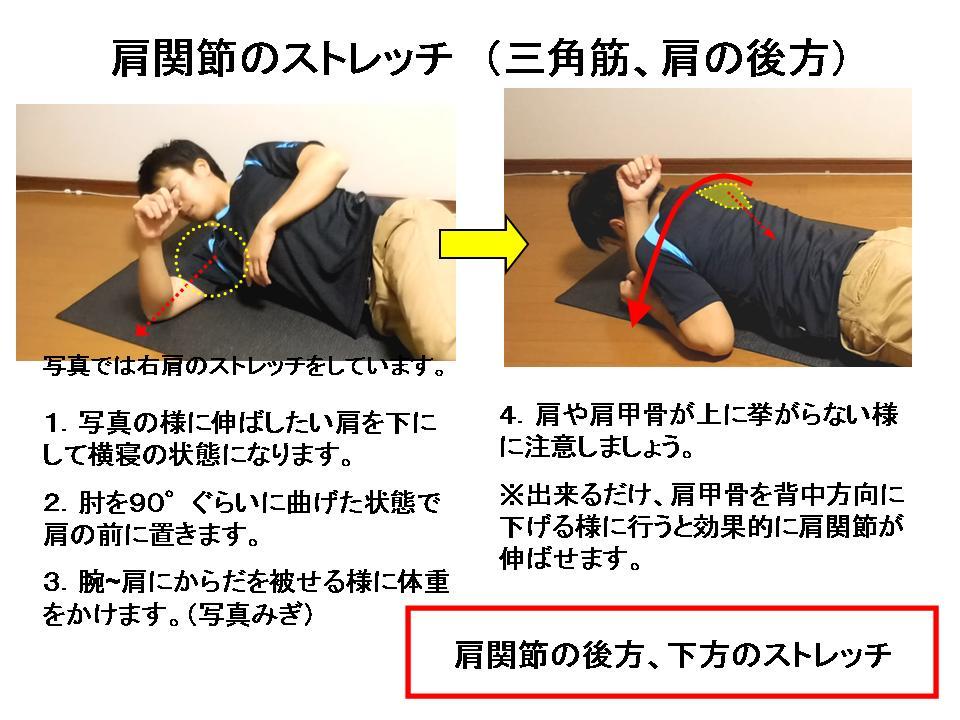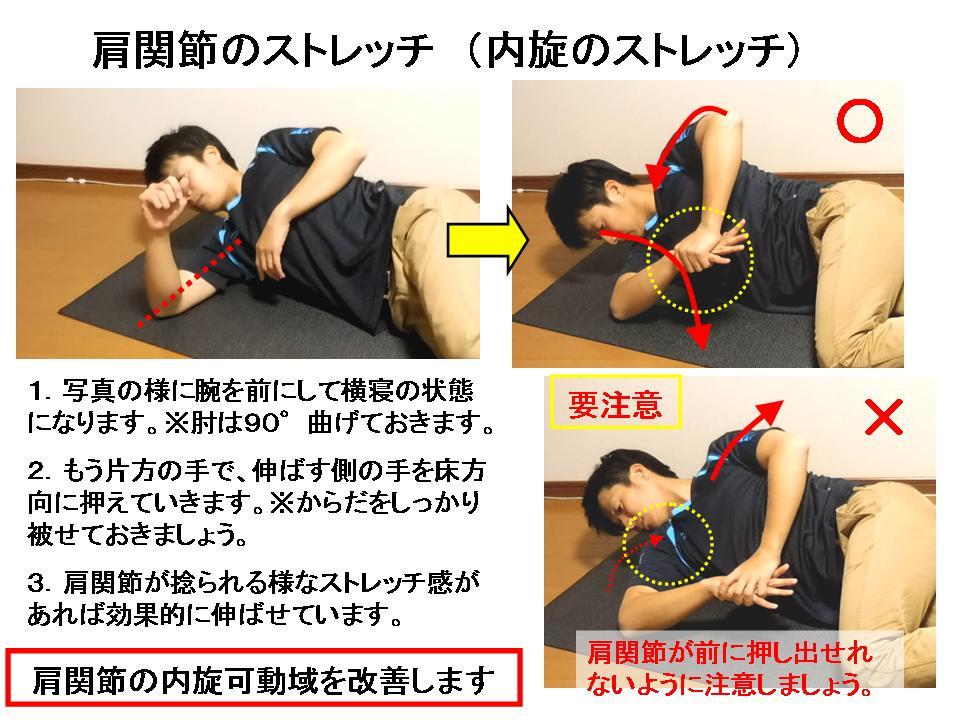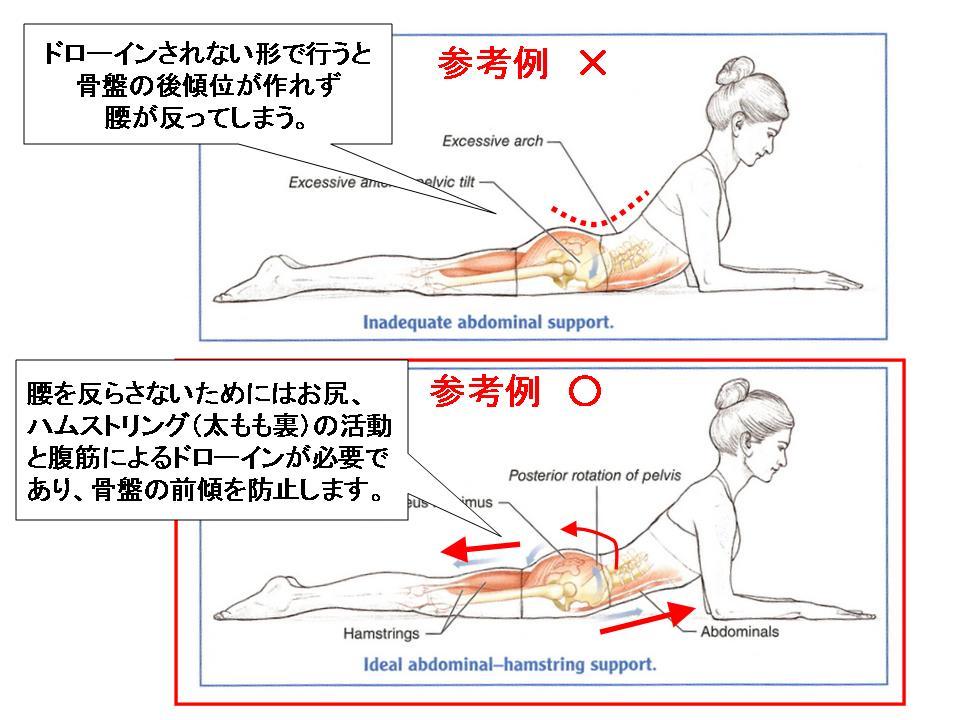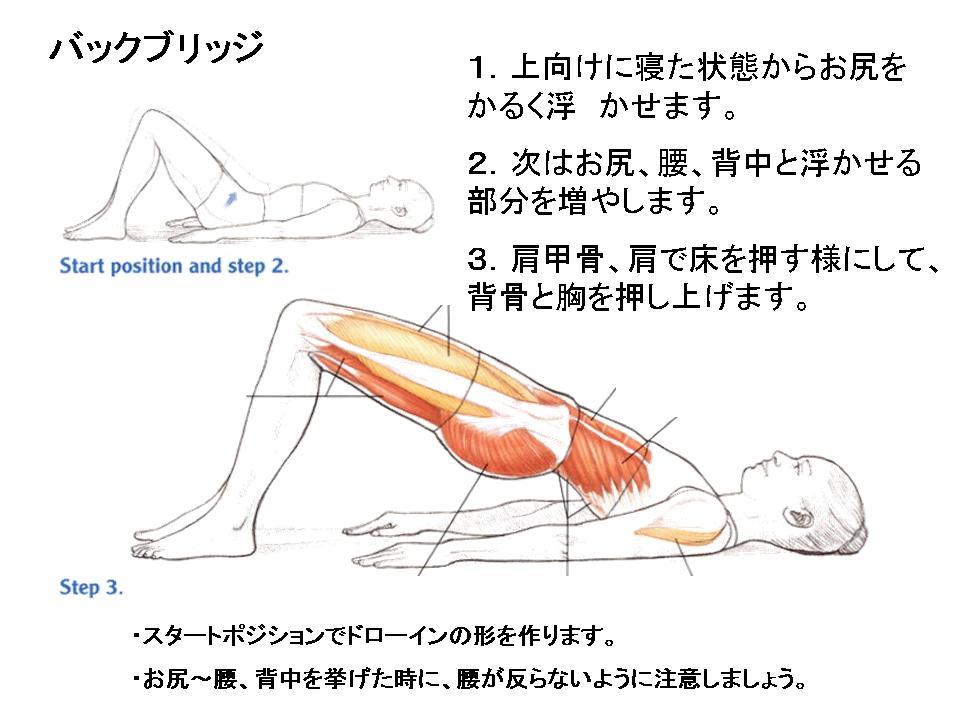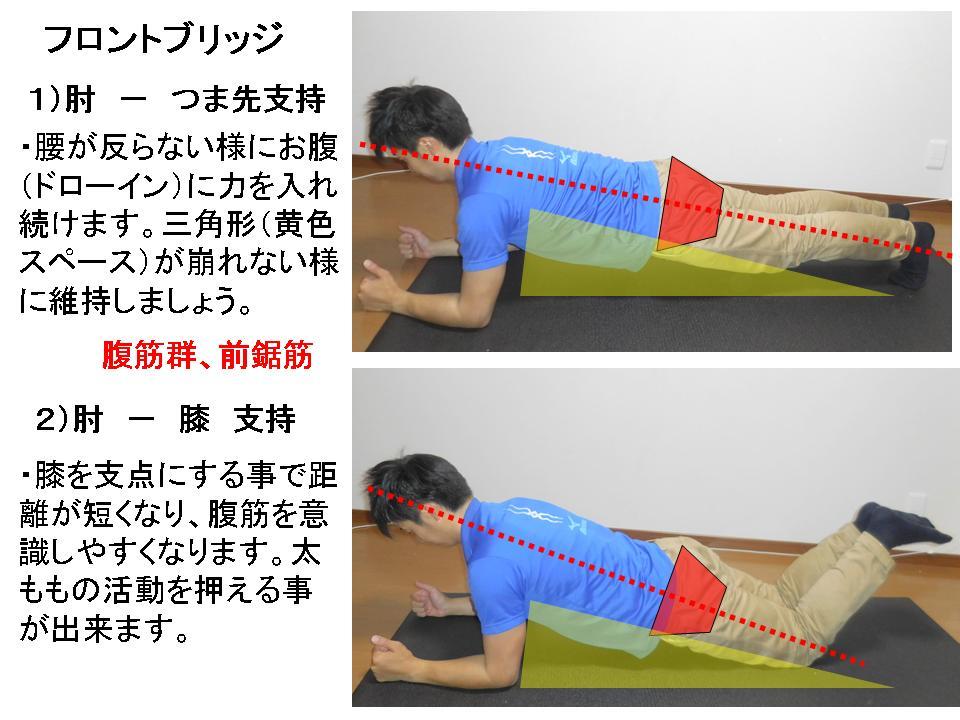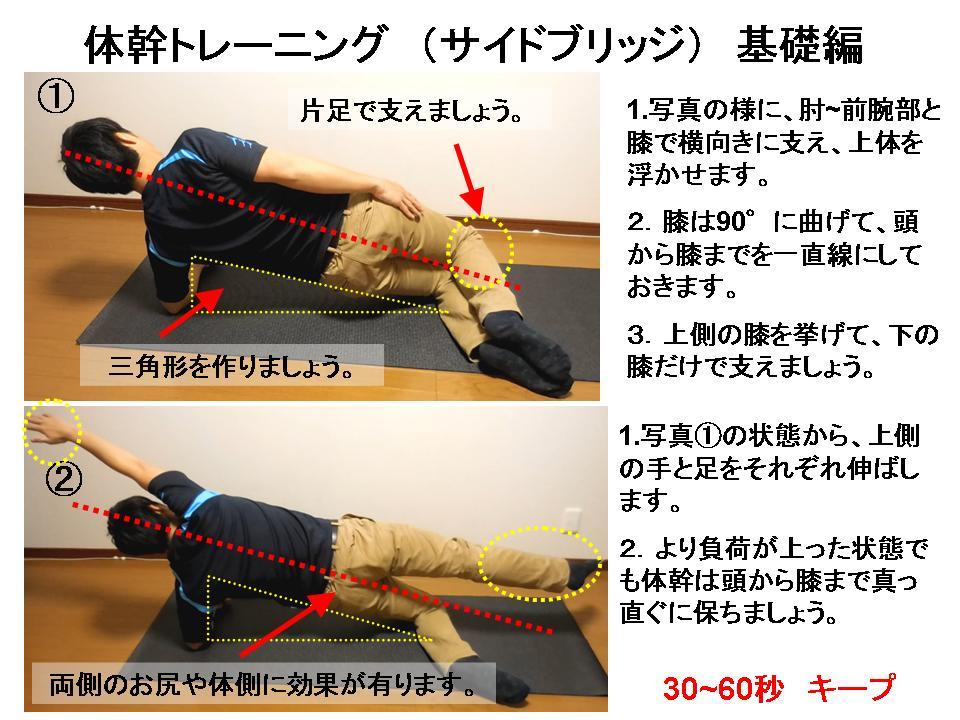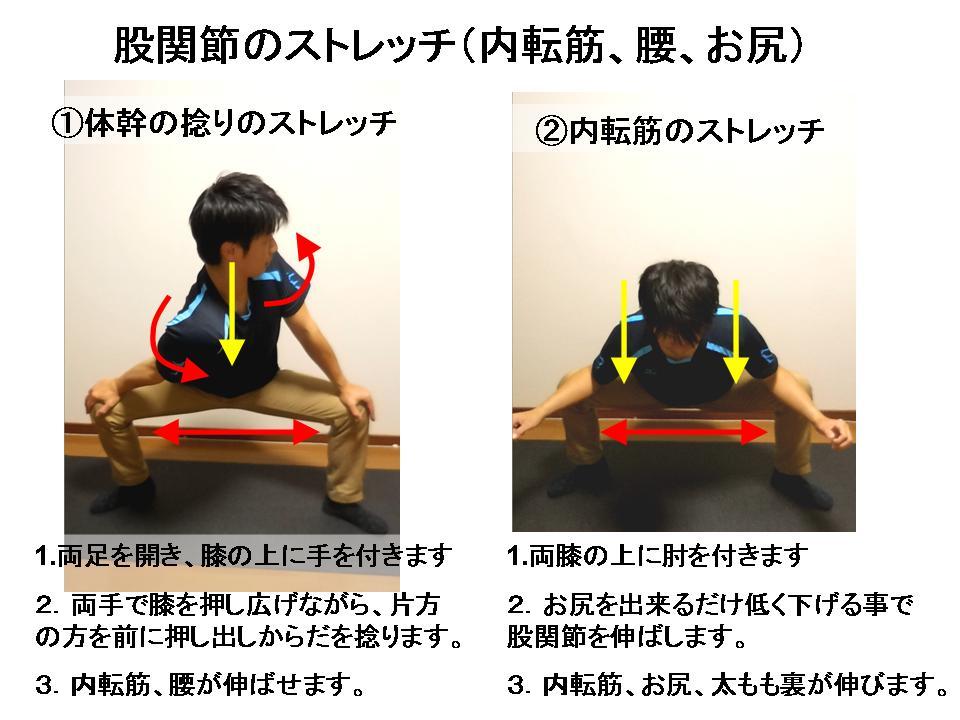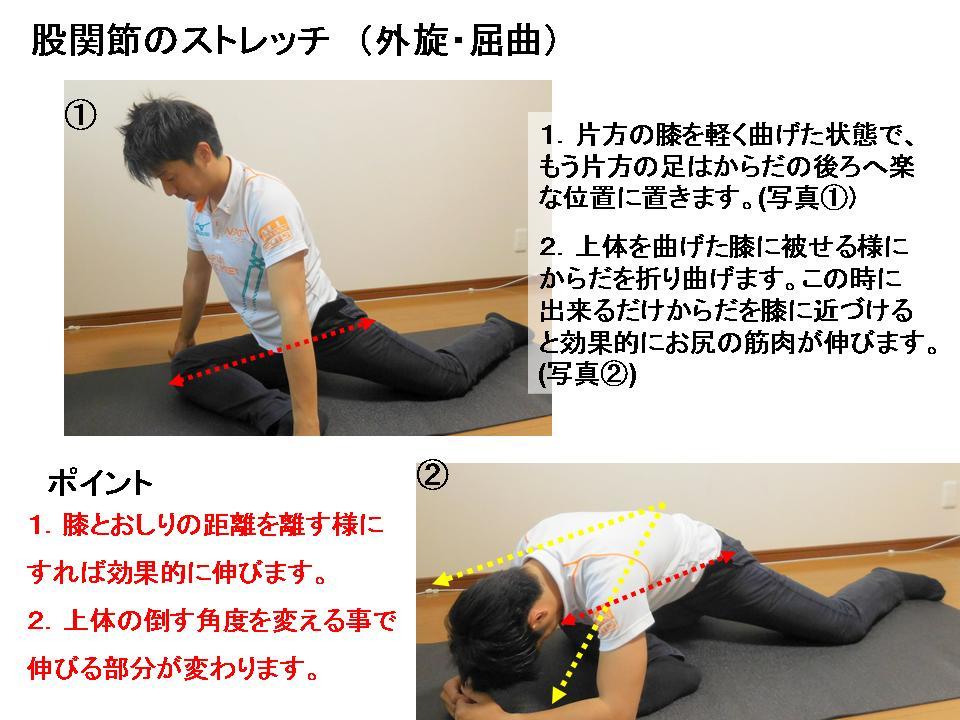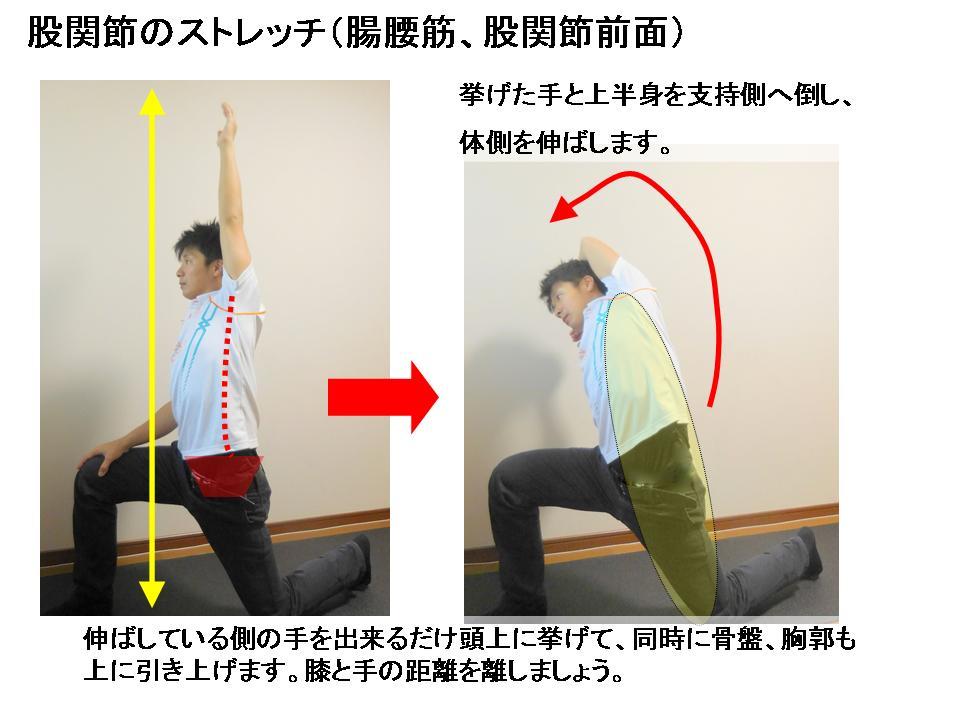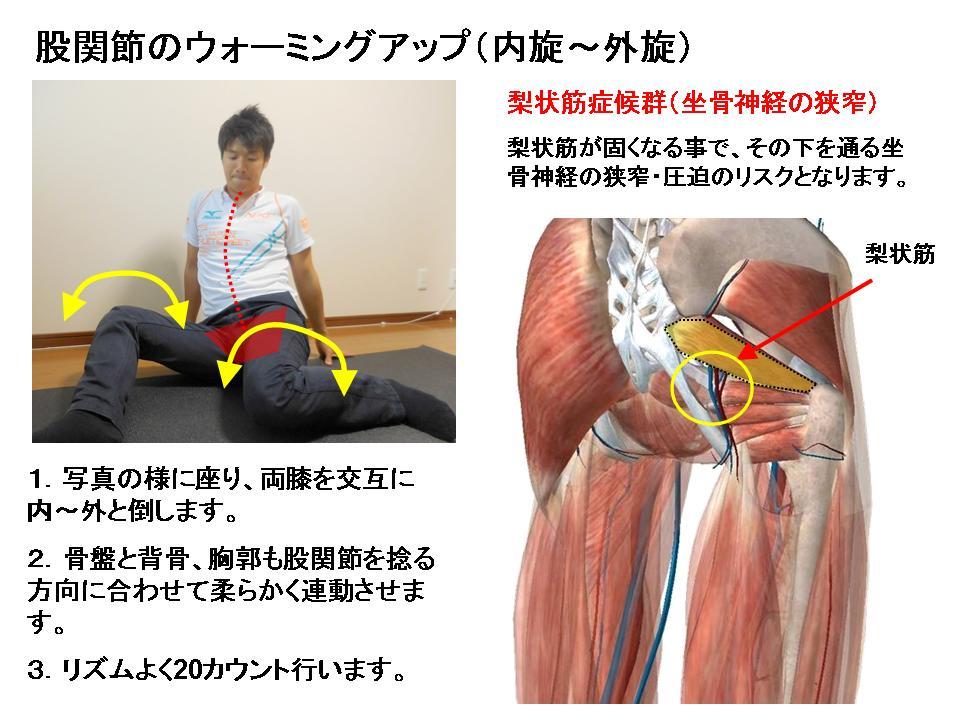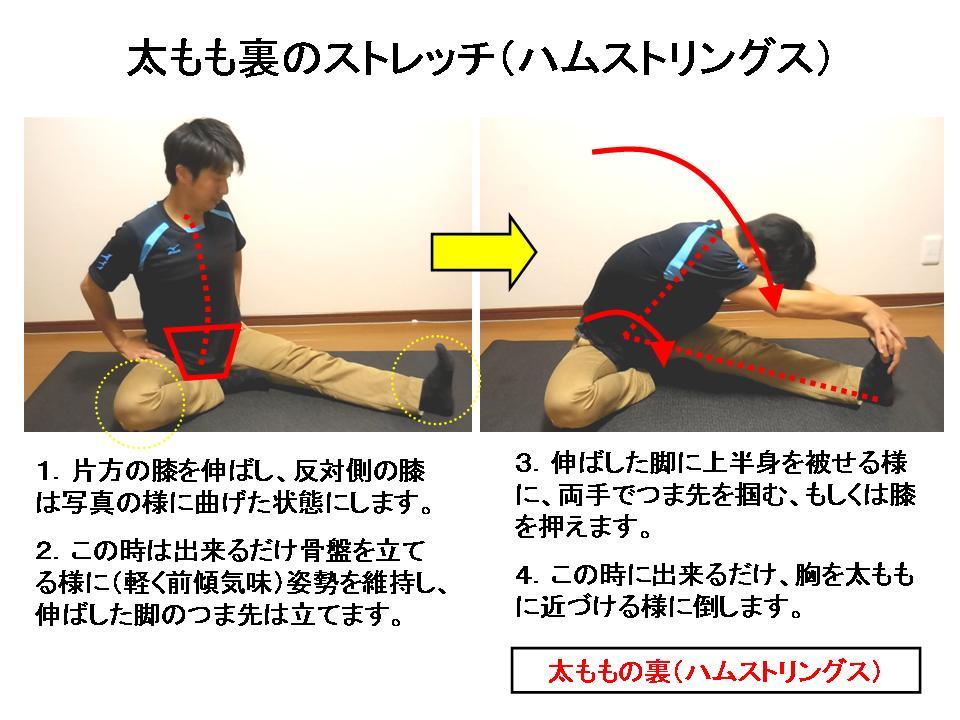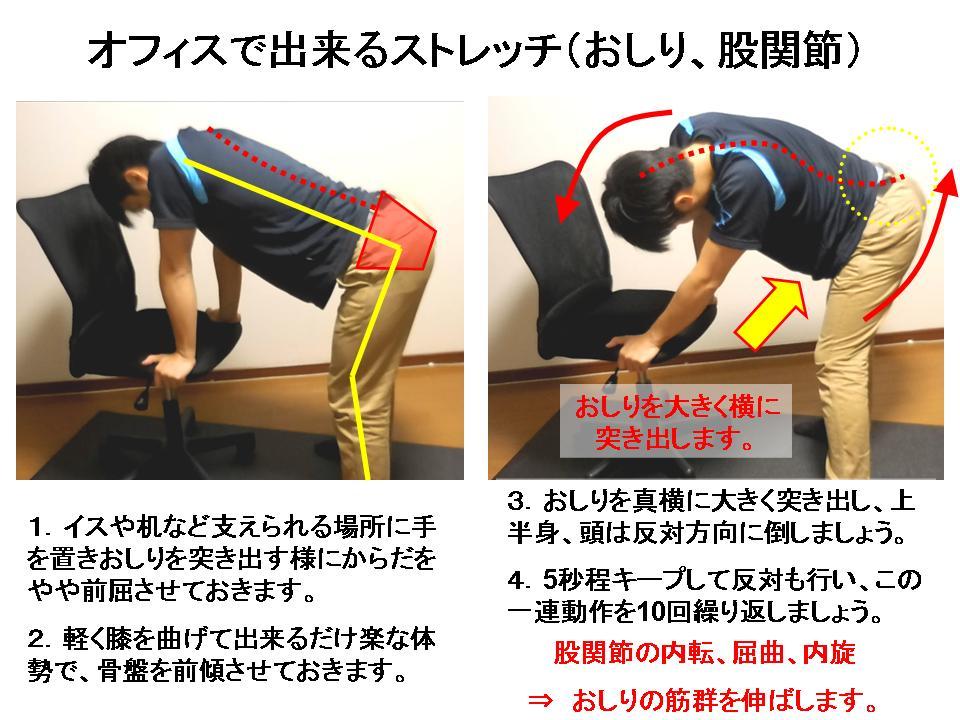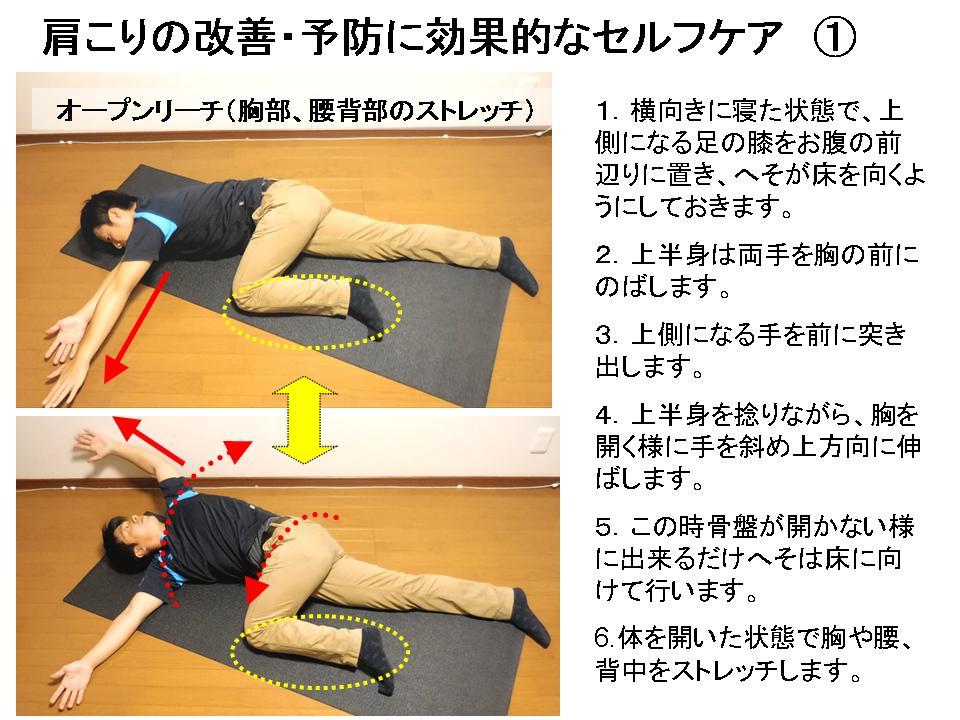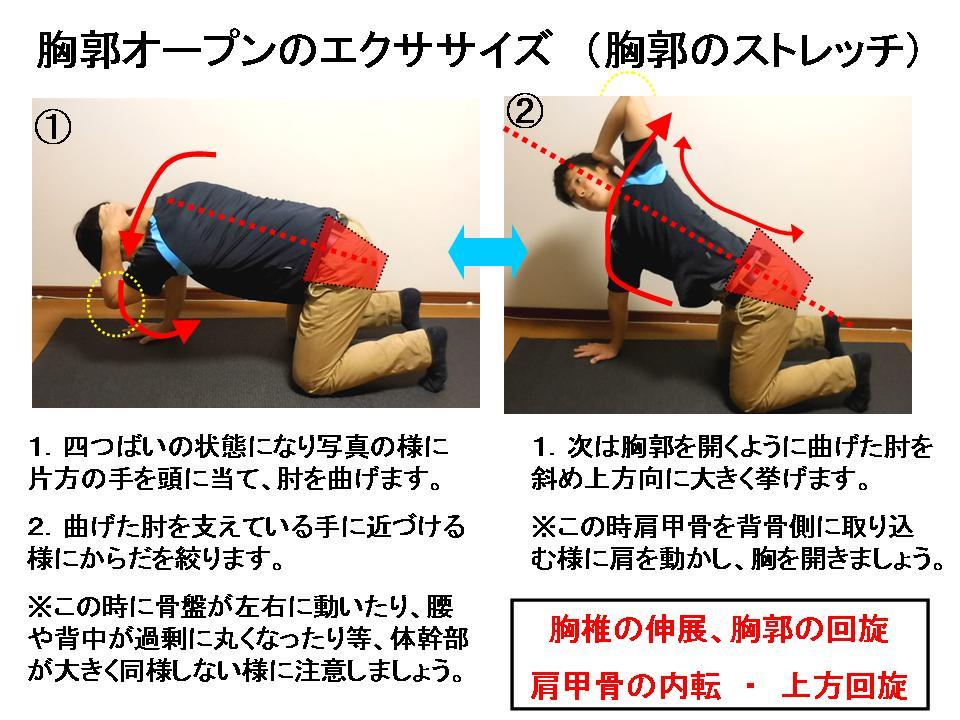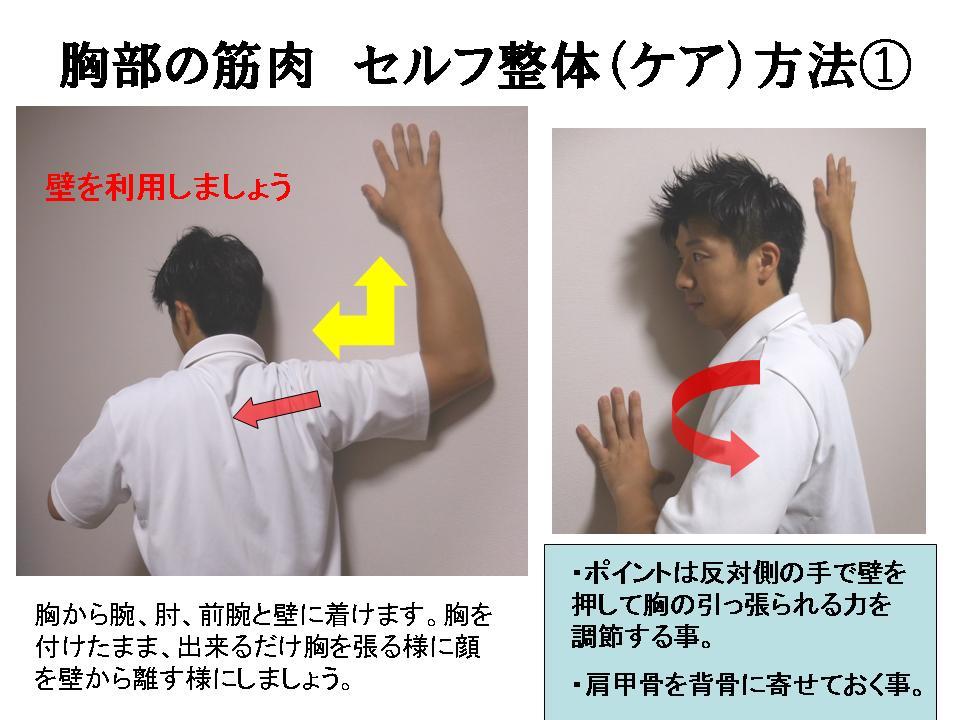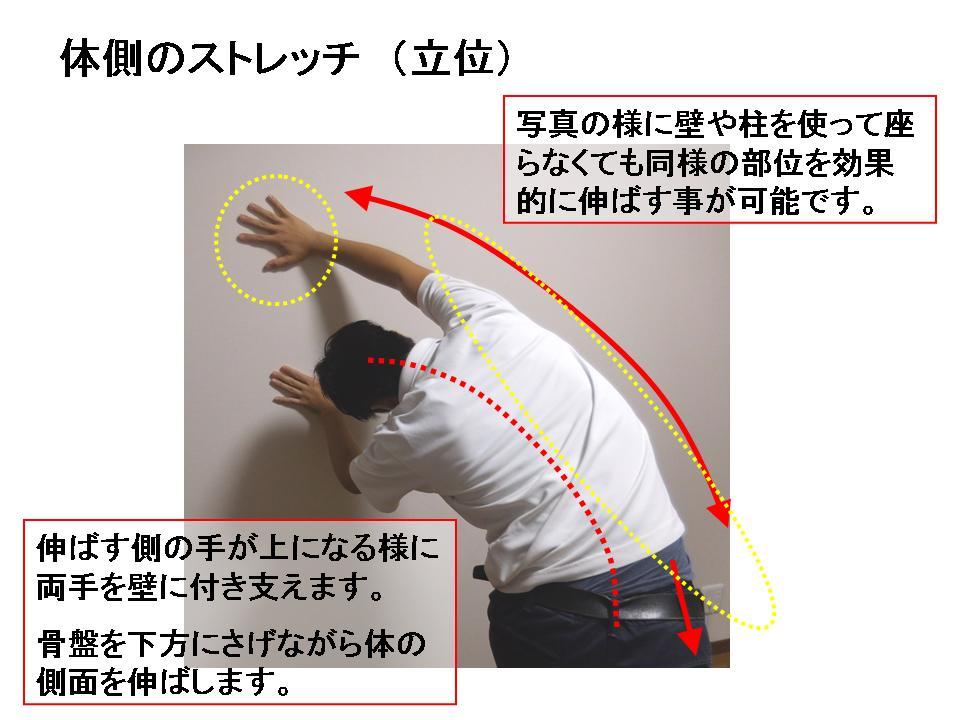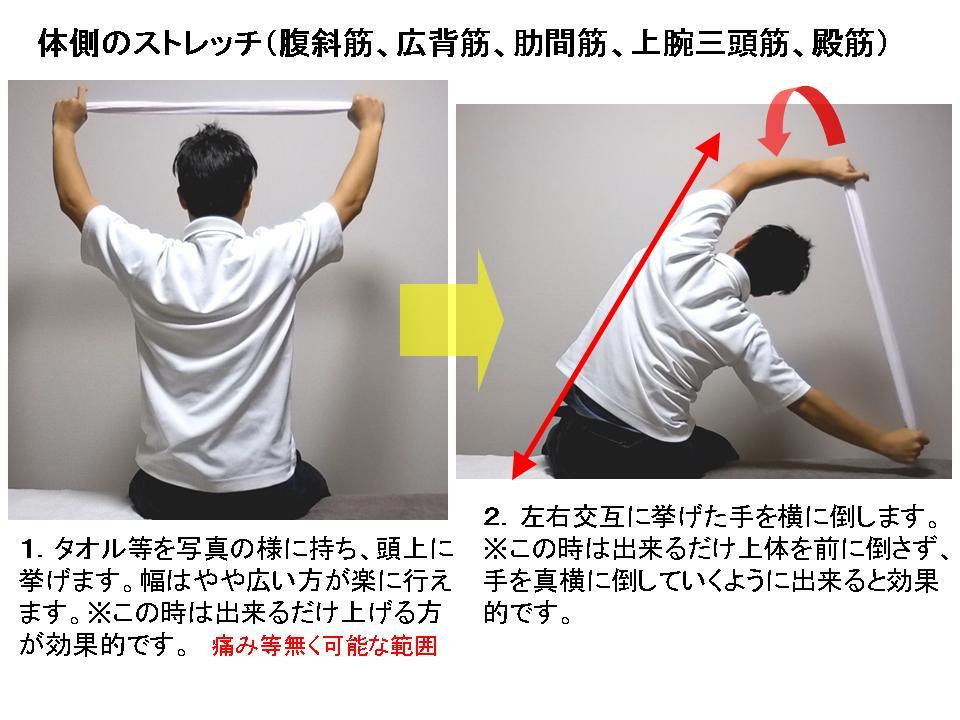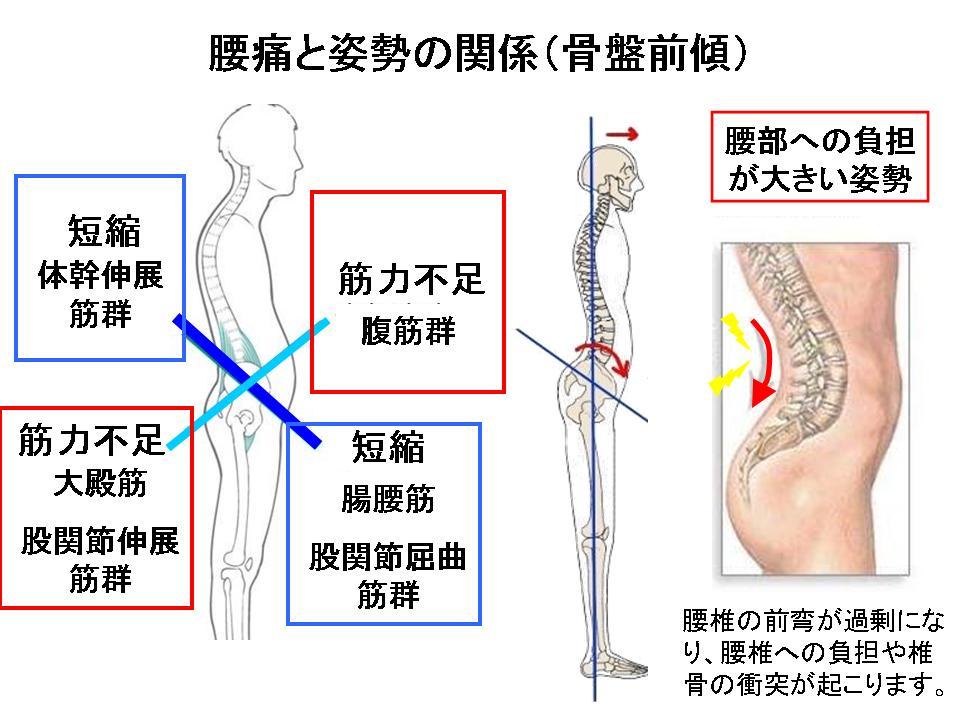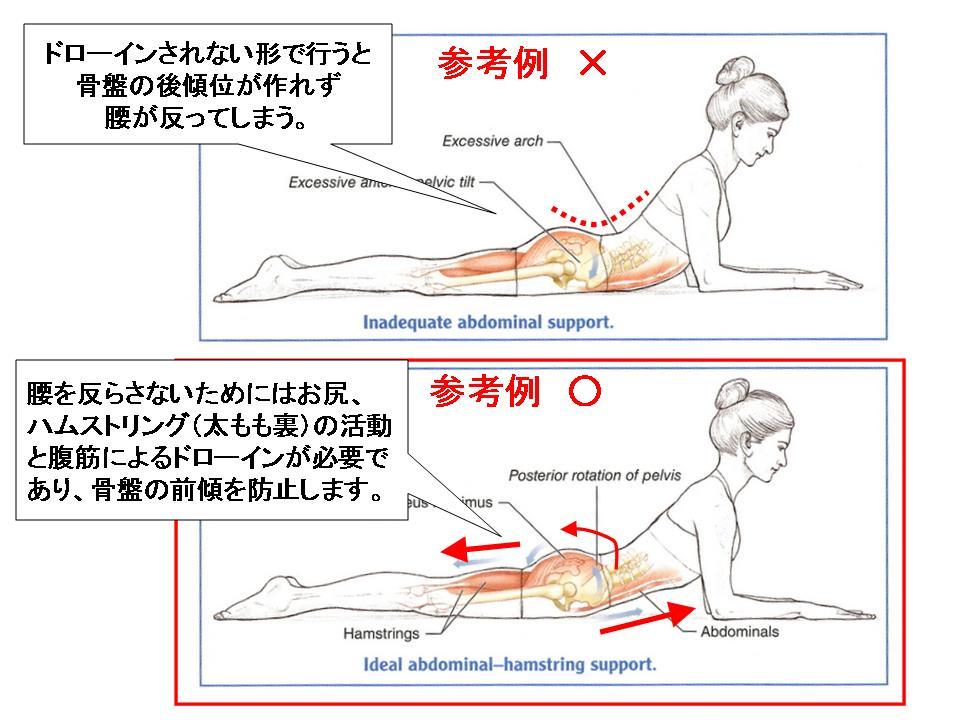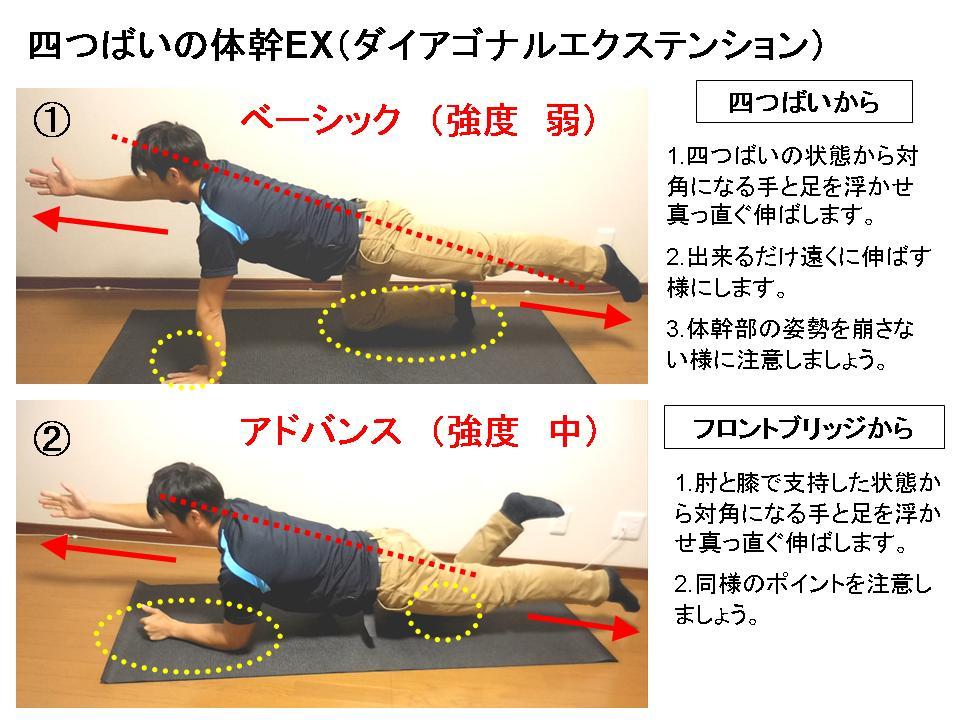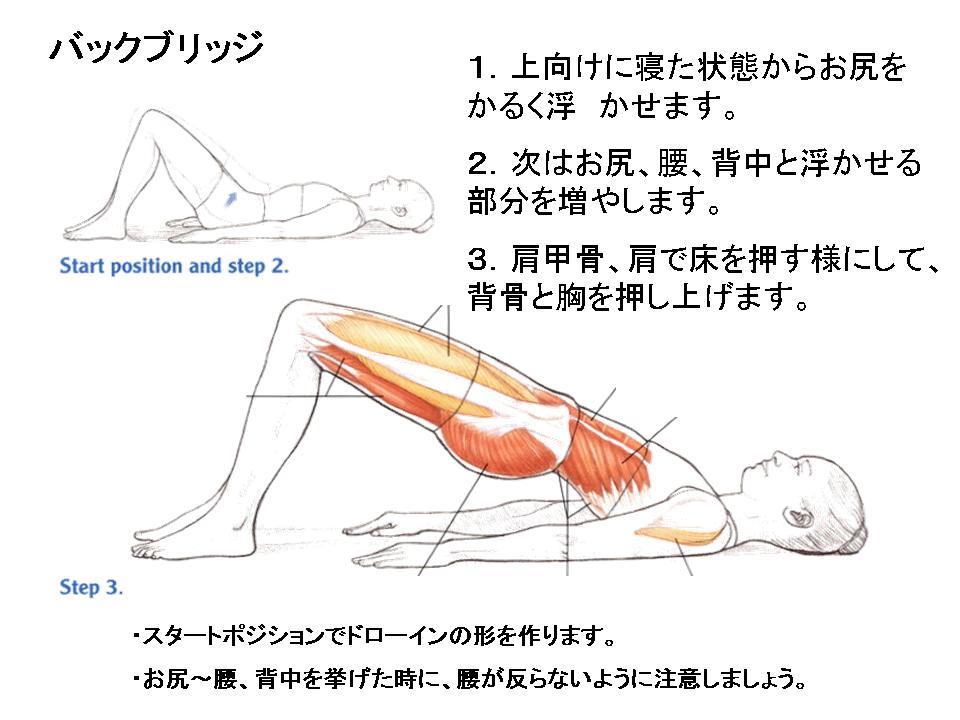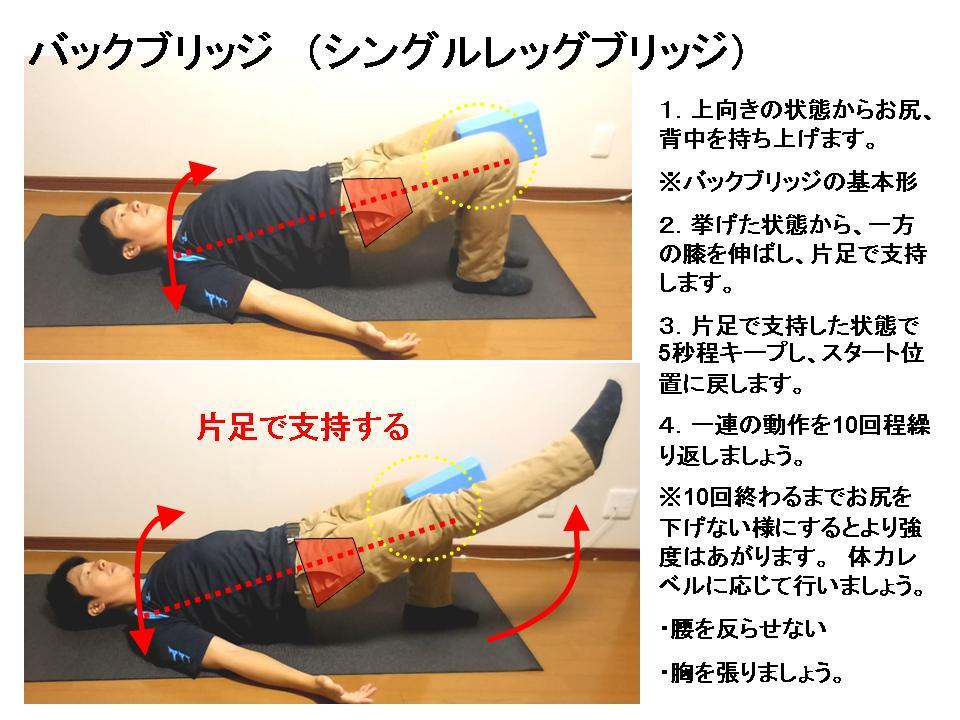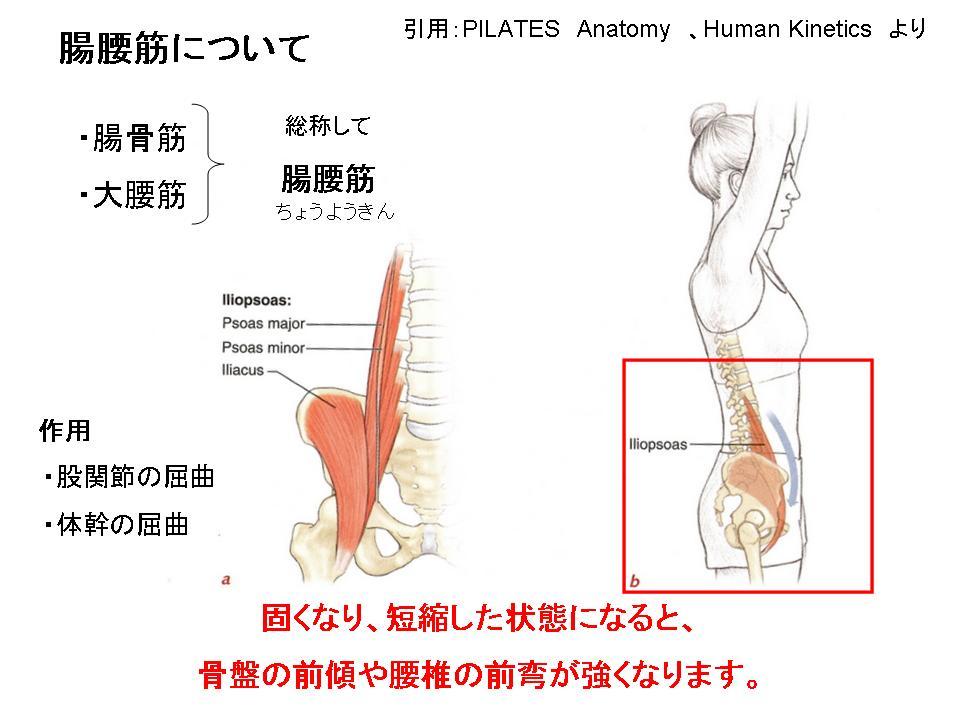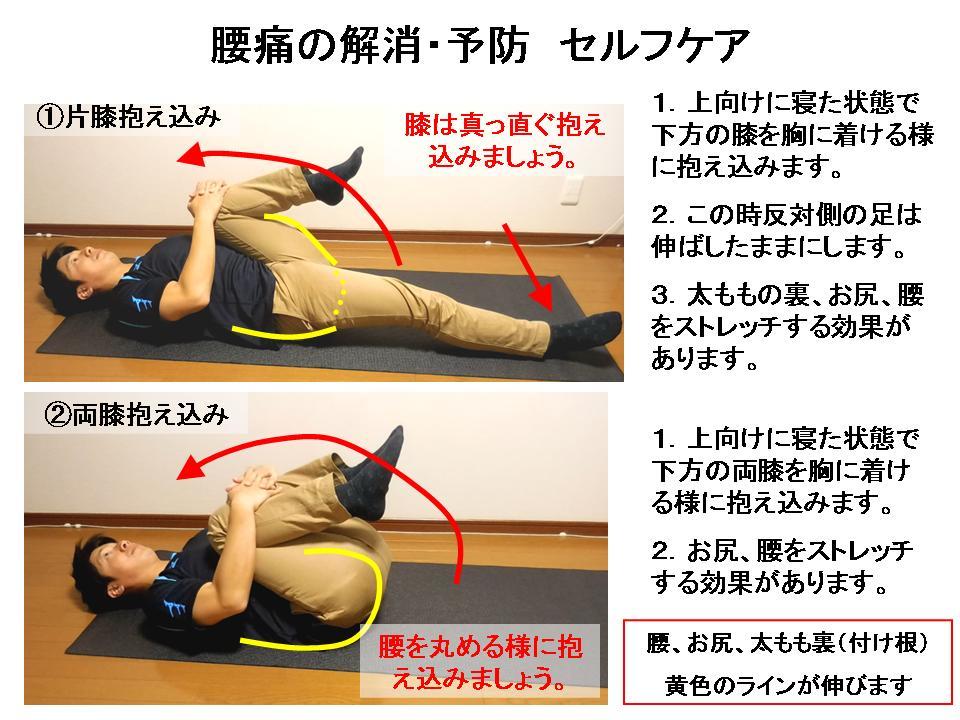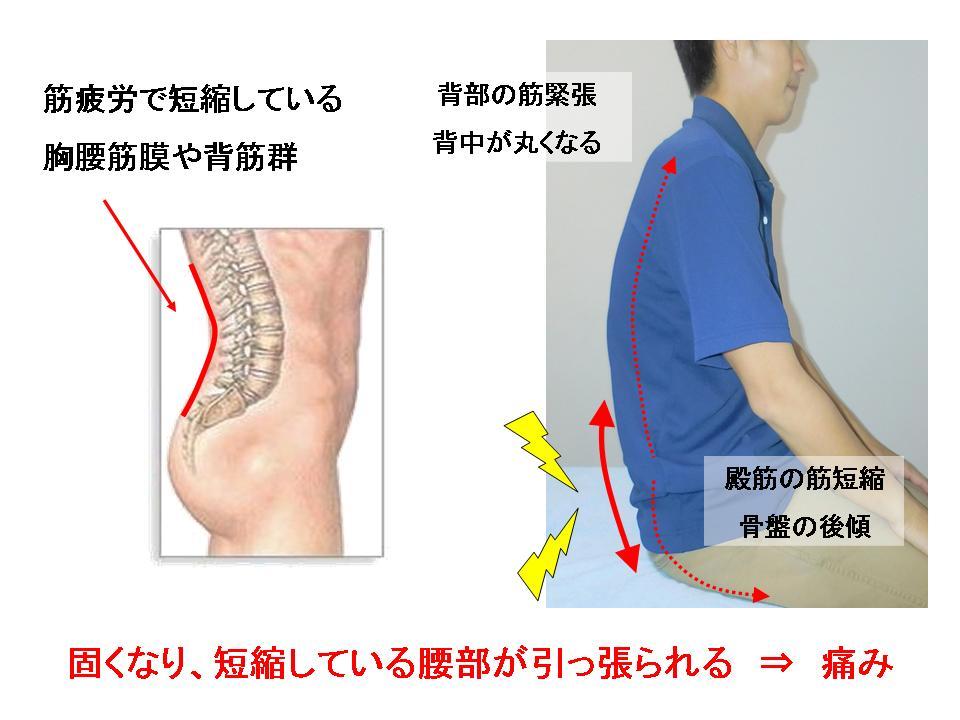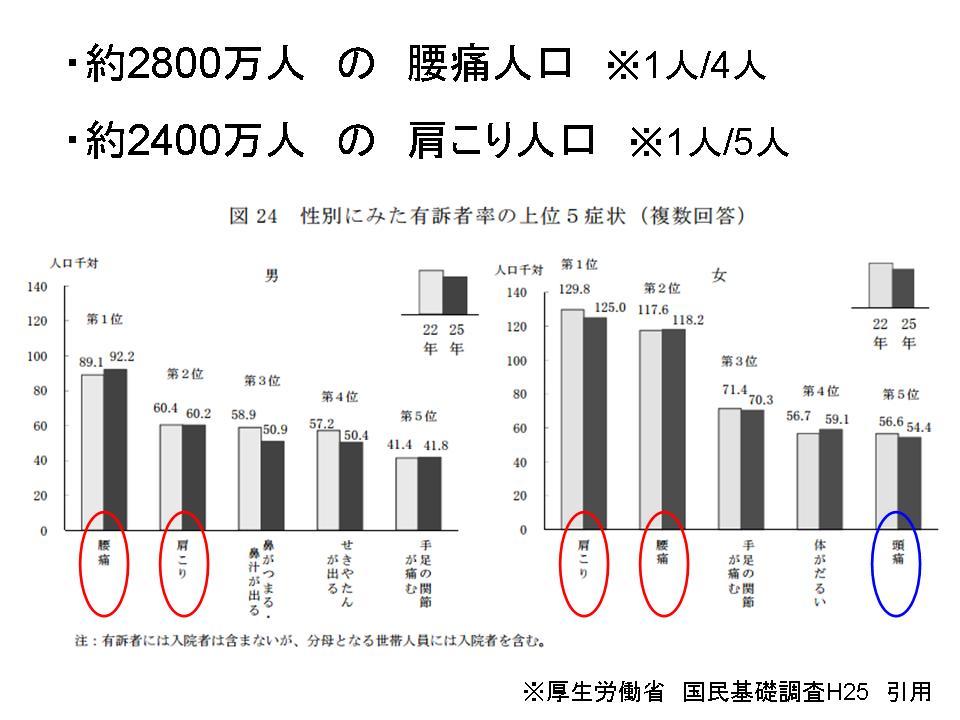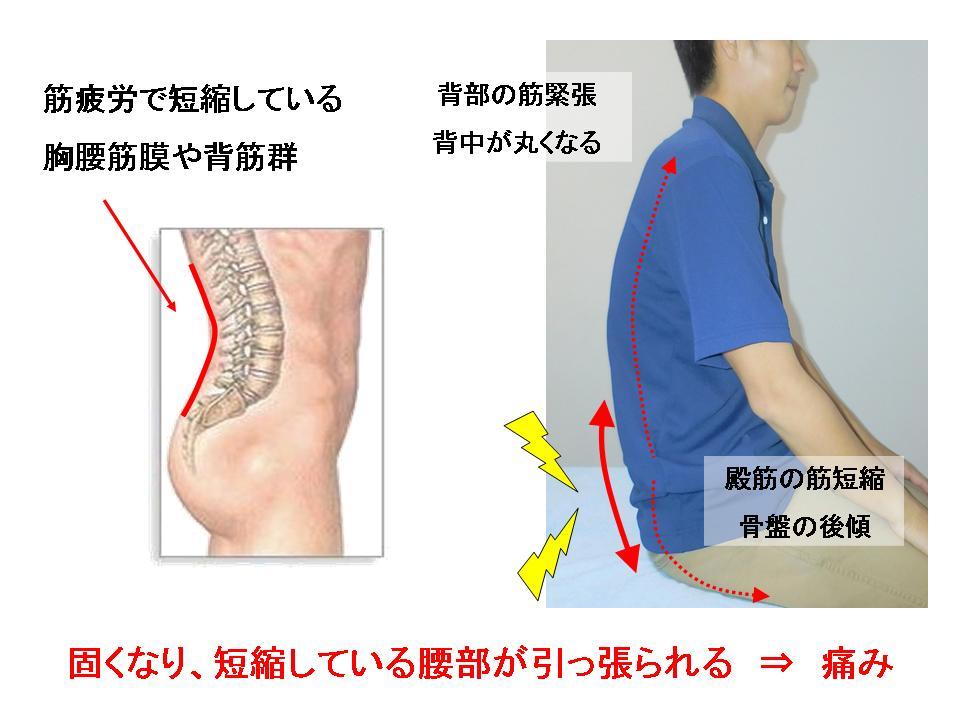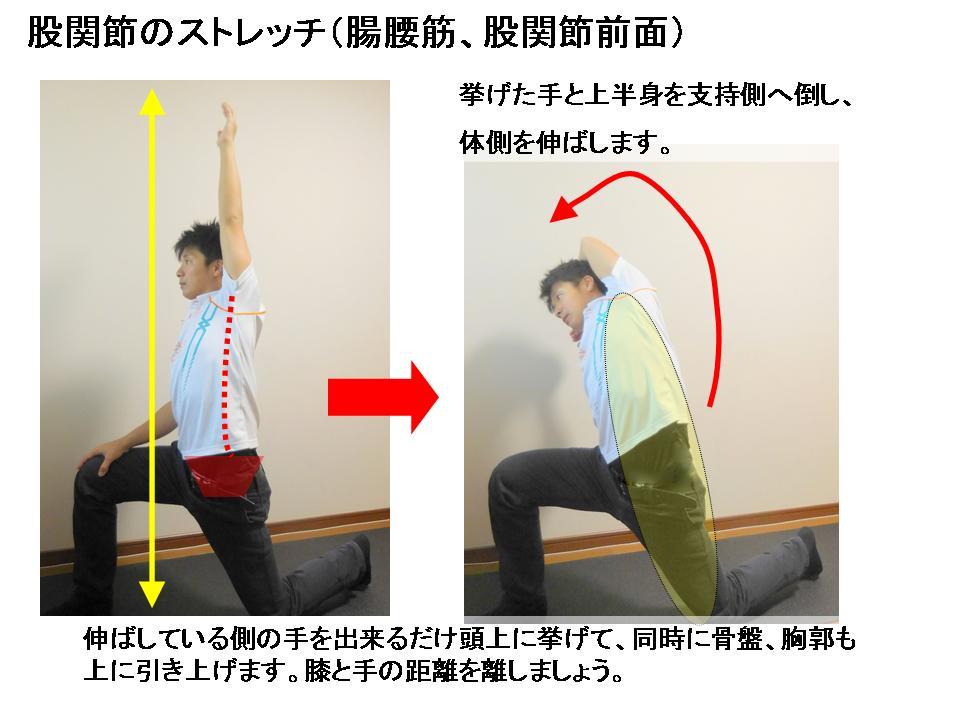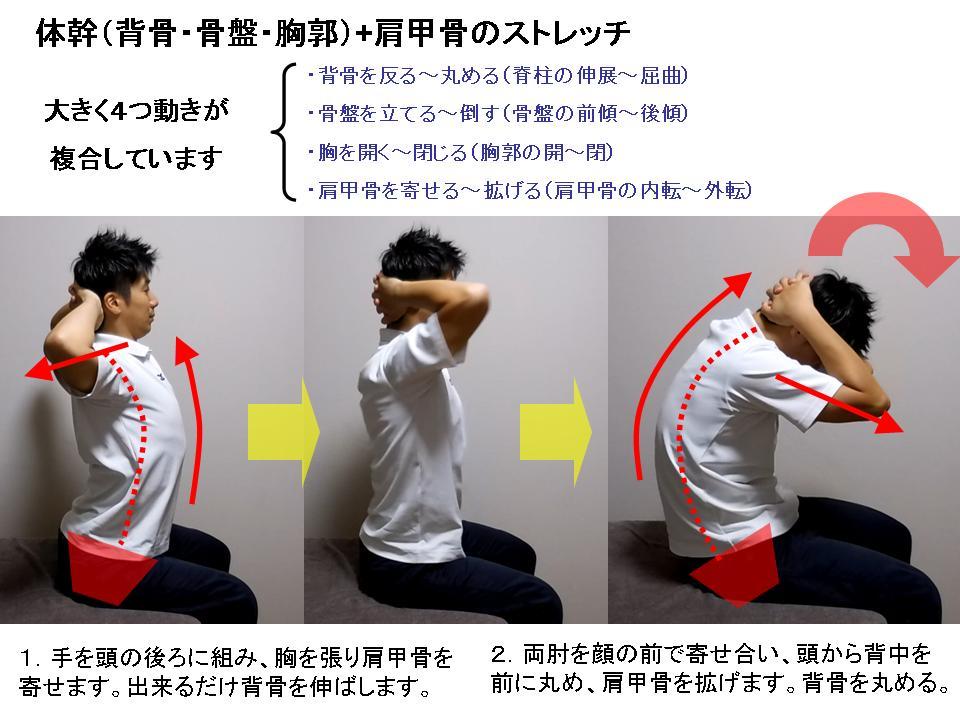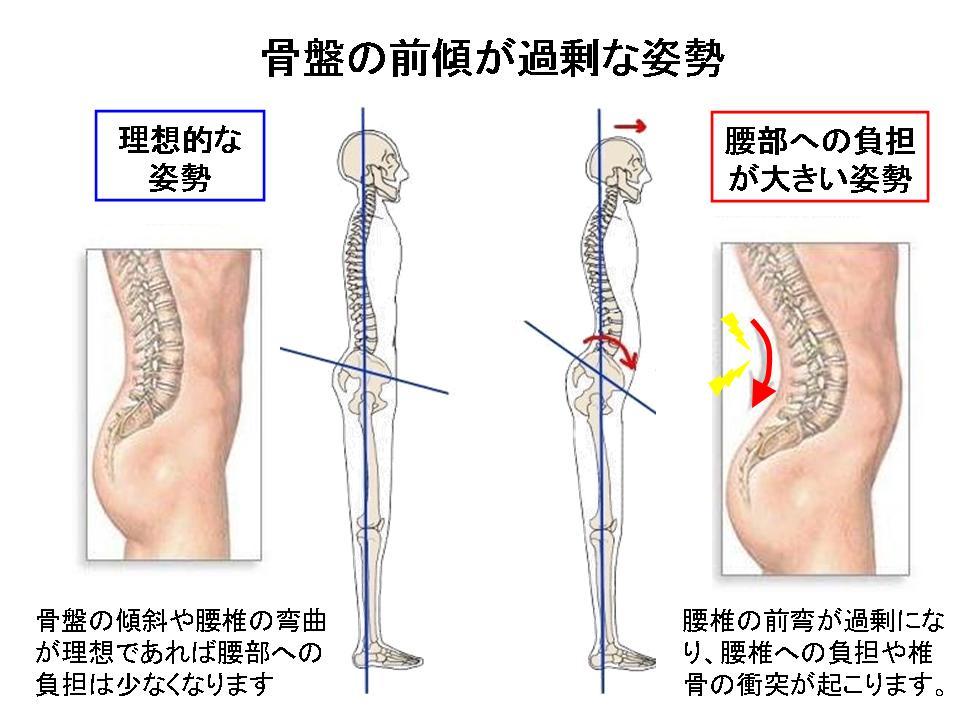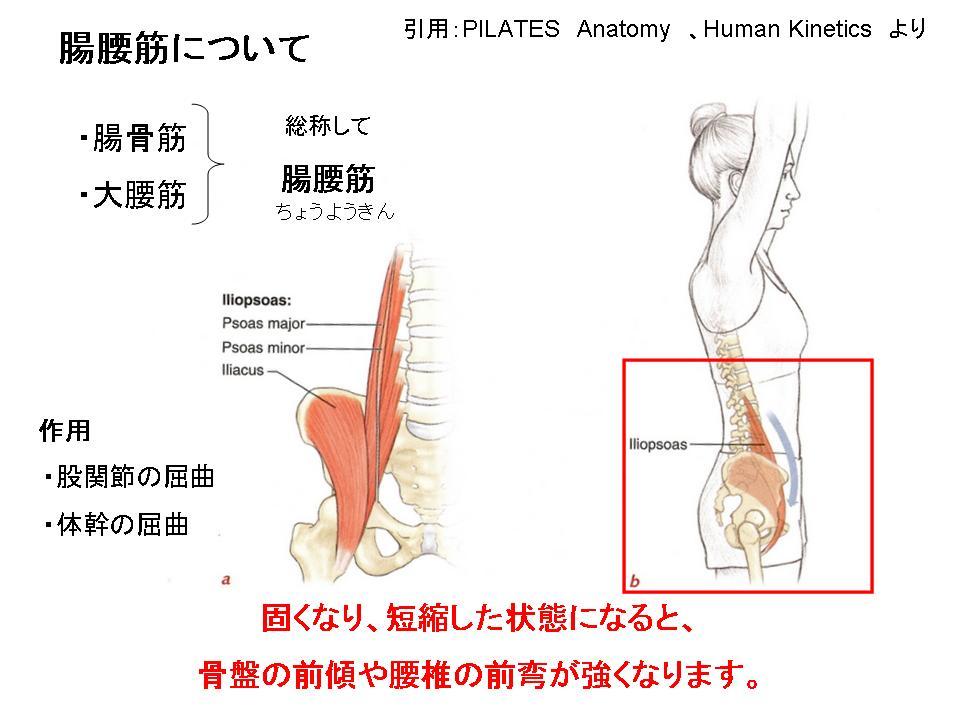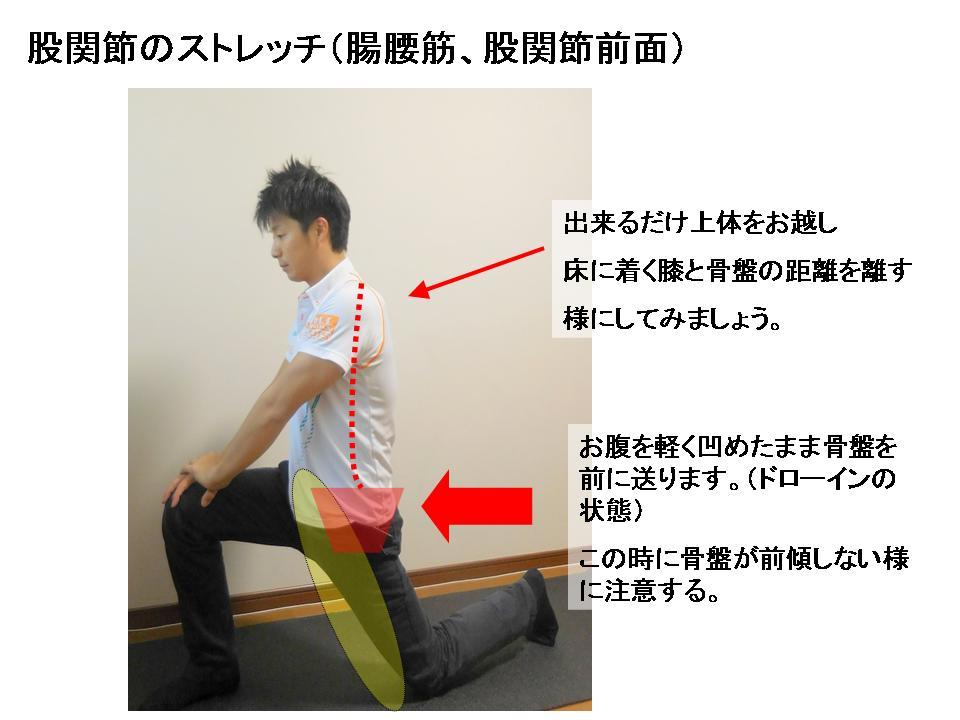今回は「体幹トレーニングの効果的な方法」No9
サイドブリッジについて第三弾をご紹介します。
前回のスタビライゼーションとはまた別の要素を
含めたトレーニングです。
強度も中強度~高強度の内容になるので
アスリートは日々のトレーニングに
または体力作りやダイエットなど
自身のフィジカルを高め、ハイパフォーマンスを
可能にする為に活用してください。
先ずは今回解説するトレーニングからご覧ください。
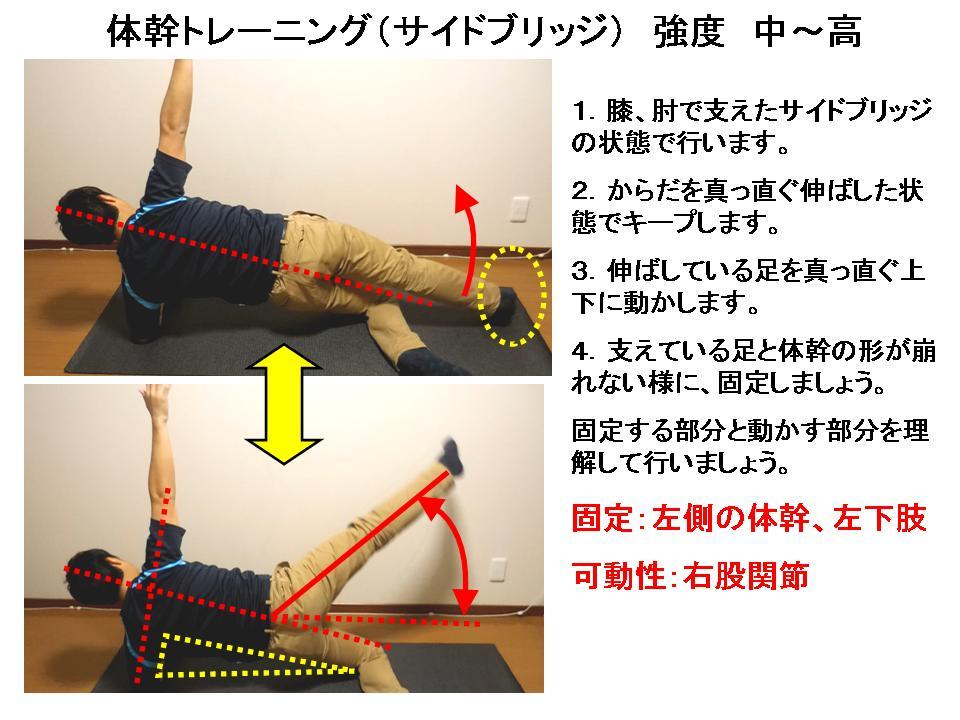
~ How to ~
1.膝~肘で支えたサイドブリッジの状態で行います。
2.からだを真っ直ぐに伸ばした状態でキープします。
3.伸ばしている足を真っ直ぐ上下に動かします。
4.支えている足と体幹の形が崩れない様に固定しましょう。
5.10~15回ゆっくり動かします。 2~3Set行いましょう。
ポイント
・支えている部分、固定する部分は出来るだけ
姿勢や形を変えずに行いましょう。
・動かす部分は出来るだけ力まず、可動性を意識して
動作を行いましょう。
・止める部分と動かす部分を理解して取り組みましょう。
効果
体側、お尻(殿筋)、背筋、広背筋の強化
写真の状態では
固定:左体側、左下肢、股関節
可動性:右股関節
が要素として含まれています。
今回ご紹介した内容は
トレーニングの要素に
安定性(Stability:スタビリティ)
可動性(Mobility:モビリティ)
が含まれております。
この2つの要素は
運動をより効率よく、安全に行うために
重要なポイントであり、からだの部位や
関節によって、運動時に求められる役割があります。
~競泳に関して~
例えば競泳選手がストロークを大きくしようと
肩関節、肩甲骨の可動性を意識したとします。
この場合水を押える際に肩甲骨が安定しないため
プルのエネルギーが効率よく推進力に繋がりません。
肩甲骨は柔軟性は必要ですが、動作の中では
安定する事が必要です。
もし安定性に欠ける場合は肩の故障に繋がったり
パフォーマンスの低下に関係します。
よく選手からも
「肩甲骨が使えていない」
「肩甲骨から動かせていない」
など肩甲骨にフォーカスした言葉や
質問を耳にしますが、ここでの
肩甲骨の安定性と可動性を間違ってはいけません。
競技レベルの高い選手は自然とからだで理解している
様ですが、柔軟性や関節弛緩性の高い選手、
特に女子選手はこの安定性を理解して
取り組む事でパフォーマンスアップと
障害予防が出来ると思います。
またこの点は今後詳しく説明していこうと
思います。